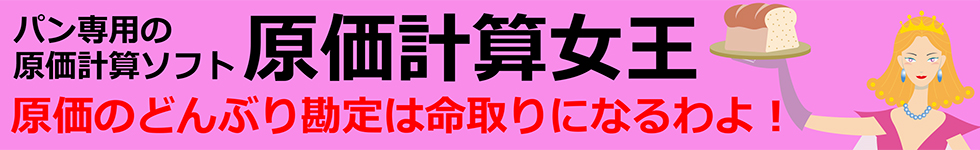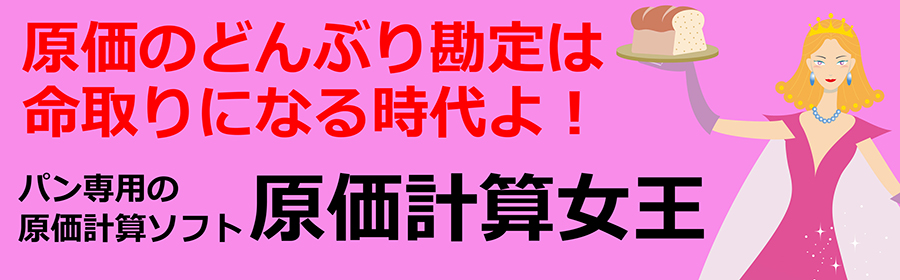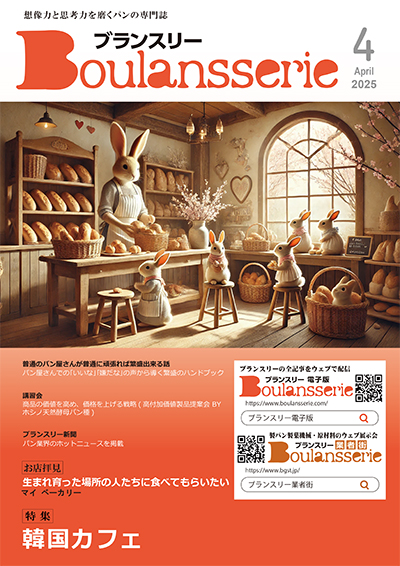記事の閲覧
| <<戻る |
| 実践的ベーカリーマネージメントの基礎知識/2004年7月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| 実践的ベーカリーマネージメントの基礎知識(4)
文・折井英雅
昭和30年に東京農工大学農芸化学科を卒業し、(株)東急フーズ(現サンジェルマン)入社、サンジェルマン開発部長、海外事業部長として国内外約120店舗のインストアベーカリー、レストランベーカリーの企画から開店までをプロデュース。平成3年ハワイ・ディーライトベーカリーでの2年間の社長職の後退社。平成4年から11年まで食糧学院・東京ホテルレストランカレッジ製菓喫茶店経営科(現在、東京栄養食糧専門学校に移管)科長として専門学校の教育に従事。現在はベーカリー会社顧問のほか、名古屋文化短大食生活専攻科講師として製菓製パン理論、フードマネージメント論を講義。所属団体としてはRC・アミカル会副会長、フードシステム研究所主任研究員として「食文化から食マーケティングヘ」の視点から、同研究所の江戸を学ぶ会、新発想開発塾に研究員として参画。 |
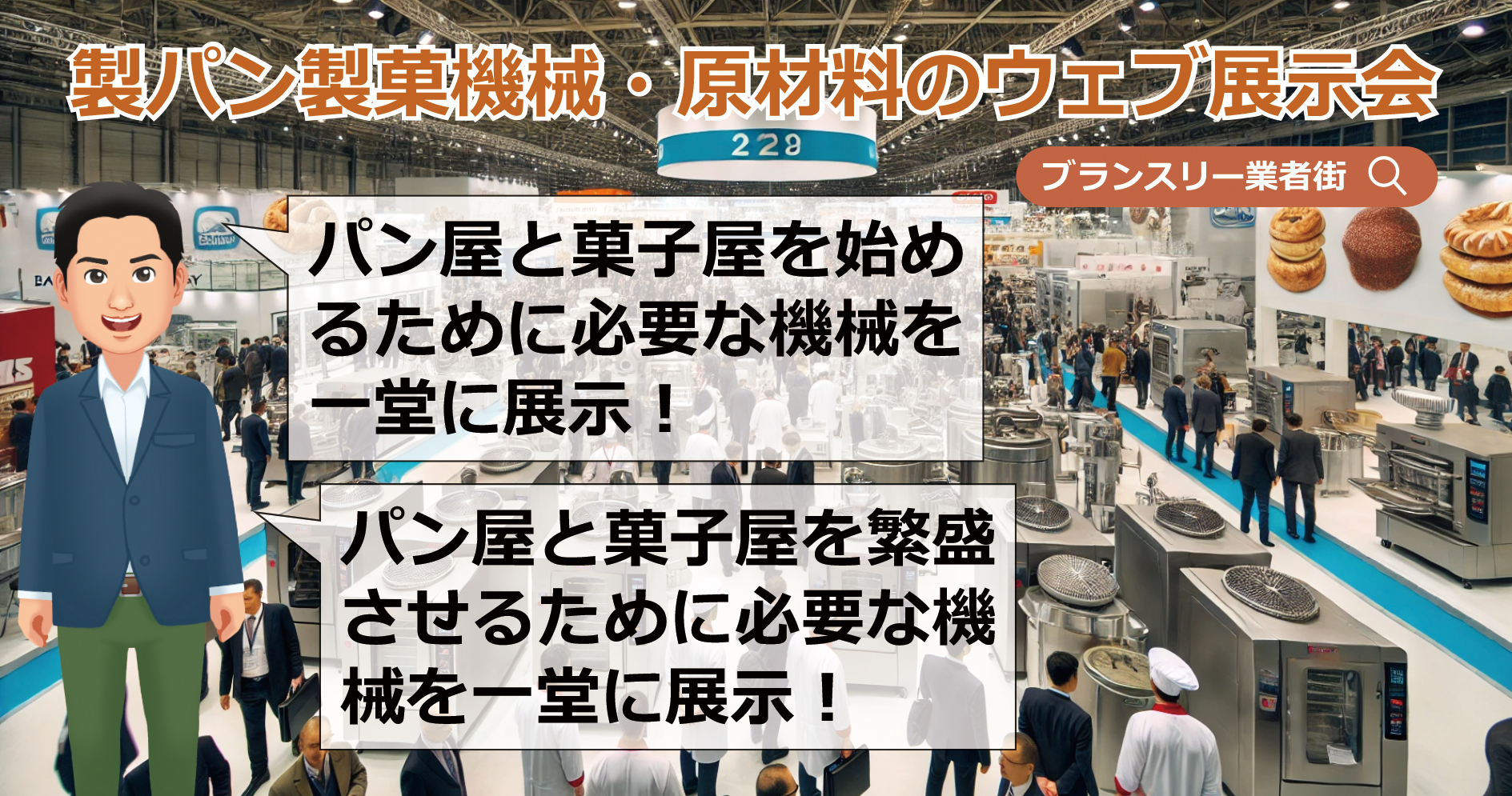
| 顧客を満足させる商品を作り、提供する過程にマーケティングが存在する
第3章 マーケティング活動
5月号(前々回)にお話しした第2章の企業運営(4月号=第1回=の図1経営系統図では先ず大項目として広義の企業経営があり次の項目に狭義の企業経営があります。その狭義の企業経営とこの企業運営は同義ですので、今後はわかりやすく企業運営で統一します)には、生産・販売活動まで入るのが順当です。しかしここでは生産・販売活動の説明は後回しにして、今回から第3章として企業継続を図るマーケティング活動を先に説明したいと思います。何故ならば企業運営をサポートして、企業継続を図るマーケティング活動の理解を先にしておくことによって、生産・販売活動に必要な売上増加策、商品開発や販売促進の考え方がよりよく解ってきますので、これらの基本的な知識をあらかじめ吸収しておきたいからです。その上で第4章で生産・販売活動についてくわしく述べたいと思います。 第1節 マーケティングとは マーケティングという言葉はよく聞きますが、いろいろの人によるいろいろの説があり、的確に表現するのは難しいことです。ここでは一般的な定義としてよく引用されているアメリカ・マーケティング協会の会長だったP・コトラー教授の定義を紹介します。 「マーケティングとは、価値を創造し、提供し、他の人々と交換することを通じて、個人やグループが必要とし、要求するものを獲得する会社的、経営的過程である。」 一寸いかめしい表現ですが、言っていることは、モノや、サービスを必要としているか(ニーズ)、または欲しがっている(ウォンツ)顧客に対して、その要求、欲望を満足させることのできる商品やサービスを、提供しようとする過程のもろもろの活動がマーケティングである、ということです。 もっと噛み砕いていえば、マーケティングのマーケットは商品やサービスが客と出会う場所、機会であり、イングは進行形ですからその動向、変化ということで、客がそこで満足してくれるように問題解決を図っていくのがマーケティングだ、ということです。工場で製造されたパンは店に並べられて、そこで客と出会います。客が必要としないパン、欲しくないパンだったら買ってくれません。その時私共は客の心理の動きや変化をよく調べて、売れるパンを作り、また売れるようにもっていかなければなりません。こうした手法や考察が、マーケティング活動ということになります。 |


| ストーリーを書けるか、シーンを描けるか、が問われる | |
|
その前に売れる商品づくり、売れる店づくりの能力とでもいうべきマーケティングセンスのことについて若干触れておきます。
皆さんのような個性派ベーカリーのオーナーシェフにとっては、新製品企画手法ともいうべき上記の過程は瞬時に自然に系統的にストーリーのように頭の中に書かれることでしょう。出来上がる商品の姿も鮮明な絵としてシーンのように頭の中に描かれ、風味についても舌の上で、感覚的に想像されるでしょう。そしてすばらしい新商品が次々と生まれることでしょう。 しかし画期的な新企画商品とか、業態開発に伴う新メニュー、新商品の開発は多くのスタッフのコーディネートが必要ですし、日常的に部下に製品開発をさせておられると思います。その場合オーナーシェフと、スタッフや部下とが同一のマインド(意識・観念)を持つこと、少なくとも同じ方向を目指すことが大切です。この場合マインドのレベルは同じでも開発された商品の出来栄えはシェフと部下とでは差が出てしまうでしょう。勿論技術力の差があるわけですから、技術の錬磨が必要ですが、それと同じようにマーケティングセンスのレベルも違い、商品の発想カ、企画力に差があるわけです。したがってスタッフや部下は、技術力アップとセンスアップの両方を心がけ、少しでもシェフに近づくよう努力していくことが大切でしょう。 このセンスアップ(感性を磨くこと)を図るためには、具体的にはどうすれば良いのでしょうか。このことについては第1回のコラムでも少し触れておきましたが、これをセンス系統図(表7)で表現しながら説明しておきましょう。 バゲットの例で考えてみましょう。バゲットといわれて先ず頭に浮かぶシーンは何でしょうか?一般の人は、クープの入った棒状の姿でしょう。フランスパンの好きなお客さんは、窯から出て「パンシャンテ」と呼ばれる、あのぴちぴちはじける音をたてながら籠で運ばれてくる生き生きした姿でしょう。専門家は良い発酵状態のバゲットの姿として、底面積の少ない丸くもりあがった形を頭に描き、食感については、皮は硬いが薄くばりばりとしていて、中身は薄い膜が適度に張ったやや塩味の感覚を舌の上で想像するでしょう。さらにお店の関係者はバゲットを中心に今より更にきれいに品揃えされた棚を思い浮かべるでしょう。またカスクルートをメニューに加えたカフェも見えるかも知れません。こんな店にしたいという全体の雰囲気が頭の中に絵となって表れるでしょう。 技術者であれば、バゲットの伝統的な製法から近代の改良法までが頭に組み立てられているでしょうし、新しい粉等の新素材の活用法も系統的に解っていることでしょう。商品開発を念頭に置いて、製法と材料の適性などが頭の中で網目状につながっていると思います。 経営者は最近のバゲットの売れ行きの情報等も収集、分析していることでしょう。もっと売上を上げるためには「特徴のあるバゲットを」ということで、パン・トラディショナルを出そうか、などと考えるでしょう。情報が集約され、網目状になり、バゲットを中心に生産から販売までを有機的、系統的に結びつけ、企画していくことが出来るでしょう。 このようにバゲット1つとっても関わりの度合いでシーンやストーリーが違ってきます。より広くより深く情報を消化し、網目のつながりをより固くして、シーンアップ、ストーリーアップ即ちセンスアップを図ることが大切です。 食の世界ではマーケティングセンスが重要だとよくいわれます。食というものが人間が生きていくための根源にありながら、その場面が多面的になり、変化が激しくなっているからです。それではパンだったらどう考えていけばよいのでしょうか。食の世界にパンを登場させて、ストーリーが書けるか、シーンが描けるか、が問われます。センスを構成する四つの能力といわれる発想力、企画カ、構成力、演出力(表現力)を高めていくことが大事です。 その場合場合でいかにパンを考えていくかについて簡単な説明をしておきますので、皆さんも一緒に考えてみましょう。 それぞれの場合に合ったパンの在り方から、そのパンのコンセプト、材料配合工程、PRの仕方、販売、食べ方までを一連のストーリーとして系統づけられるか、それぞれの場合のパンのあるシーンが風景として頭に浮かんでくるか、ということです。 このセンスアップには、個々の商品からパン全般まで、更に関連商品についても、その文化史からプロダクト側のかたち、マーケット側のかたちまでを含めた「全商品格」(コラム参照)についてよく知っていくことが大切です。常に問題意識をもってあらゆる事象(物事・情報)を収集分析、集約して創造していかなければなりません。 |

| コラム | |
|
全商品格
人に全人格があるように個々の商品にも全商品格があると考えられます。商品は左の「全商品格表」の体系の通り、その文化史に裏付けられ、それがどこに属するかの分類がなされ、製品になるためのプロダクト側の諸々の過程を経て、商品としてマーケット側に出ます。そして包装陳列され、お客さんに評価されて買われる、というまさしくマーケティングでいうところの業態、品態にまで網目状に系統的につながっていくのです。 この文化史から左まわりに個々の過程を経て業態品態に至るまでの流れを考えること、即ち食文化の視点から食マーケティングを考えることが、新しい業態、品態発想につながっていくのです。 品態発想 「品態」という用語はまだ一般的ではありません。しかし一部マーケッターの間では大変重要視されてきました。 すでに業種に対する「業態」は一般化しております。即ち業種とはパン店、そば屋、惣菜屋、フレンチレストランというように取扱商品やメニューで分類した店の性格です。 これに対して「業態」とは、客の買う立場、使う立場から品揃え、売り方、食べ方などが検討され、それを具現化した小売、飲食形態などの態様のことです。百貨店、ファストフード、コンビニエンスストアなどがこうした発想から生まれた「業態」といえます。 これと同じように品種に対する品態を考えた時、品種は作り手側がその製品の特性や属性から分類したものですが、「品態」とは、客の購買動機、喫食動機を意識した概念で、客の前で商品の在り方がどういう態様を示しているかということを表します。 業態発想で新しいタイブの店舗がつぎつぎと出来るように、品態発想で新商品や新しい商品の提供の仕方がいろいろと考えられるはずです。 バゲットを例にしましょう。インストアベーカリーではフランスパンの品群のコーナーで籠に立てて売るのが通常ですが、客の焼きたてがすぐ欲しいという要望に応えて、窯も売場の前面に出しその前にカウンター平台を置いて、焼きたてという範疇で、フランスパンでも食パンでも並べて売るという、窯前平台活用の提供の仕方も考えられます。 ある店では、バゲット利用のサンドイッチの一品目のカスクルートの具(生ハム類、トマト等の野菜類)が、産地直送の特別品で、客からそれらを内食の材料に欲しいという要望があり、サンドイッチと食材料をあわせて売るサンド・惣菜コーナーが生まれました。 また、あるスーパーマーケットでは、包装した冷凍のバゲットを、袋の説明文に解凍の仕方、加熱の仕方を印刷しておき、パンコーナーではなく冷凍ピザ等と同じ冷凍品コーナーで売るという、客の購買動機に合わせた提供方法が考案されました。 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。