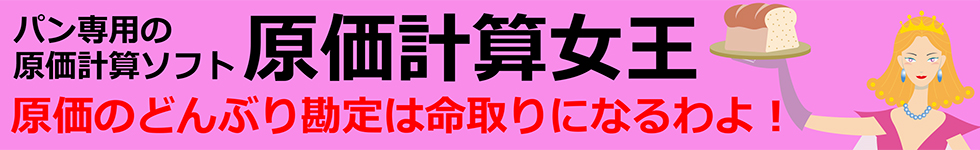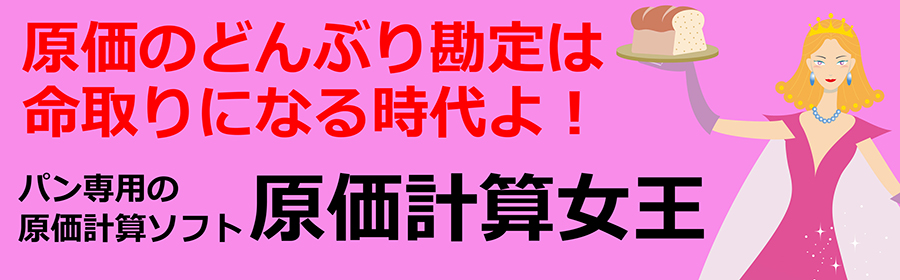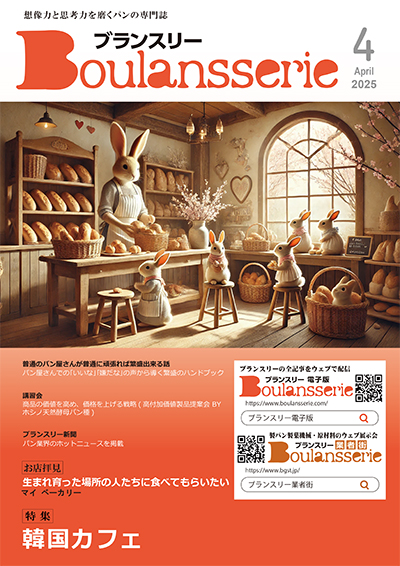記事の閲覧
| <<戻る | 写真をクリックすると拡大写真が見られます。 |
| ここにもパンの現場/2011年10月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| スーパー内パン店の憂鬱。岐路に立つインストア・ベーカリー | |
|
スーパーやショッピングセンターの中で、焼きたてパンを提供しているインストア・ベーカリー。強力な集客ツールとして各スーパーがこぞって出店したいわば「店内パン屋さん」も、消費者の節約志向の高まりもあって、かつてほどの勢いはなくなった。スーパー自体が顧客減に悩まされる昨今、インストア・ベーカリーが図る生き残り戦略とは?
|
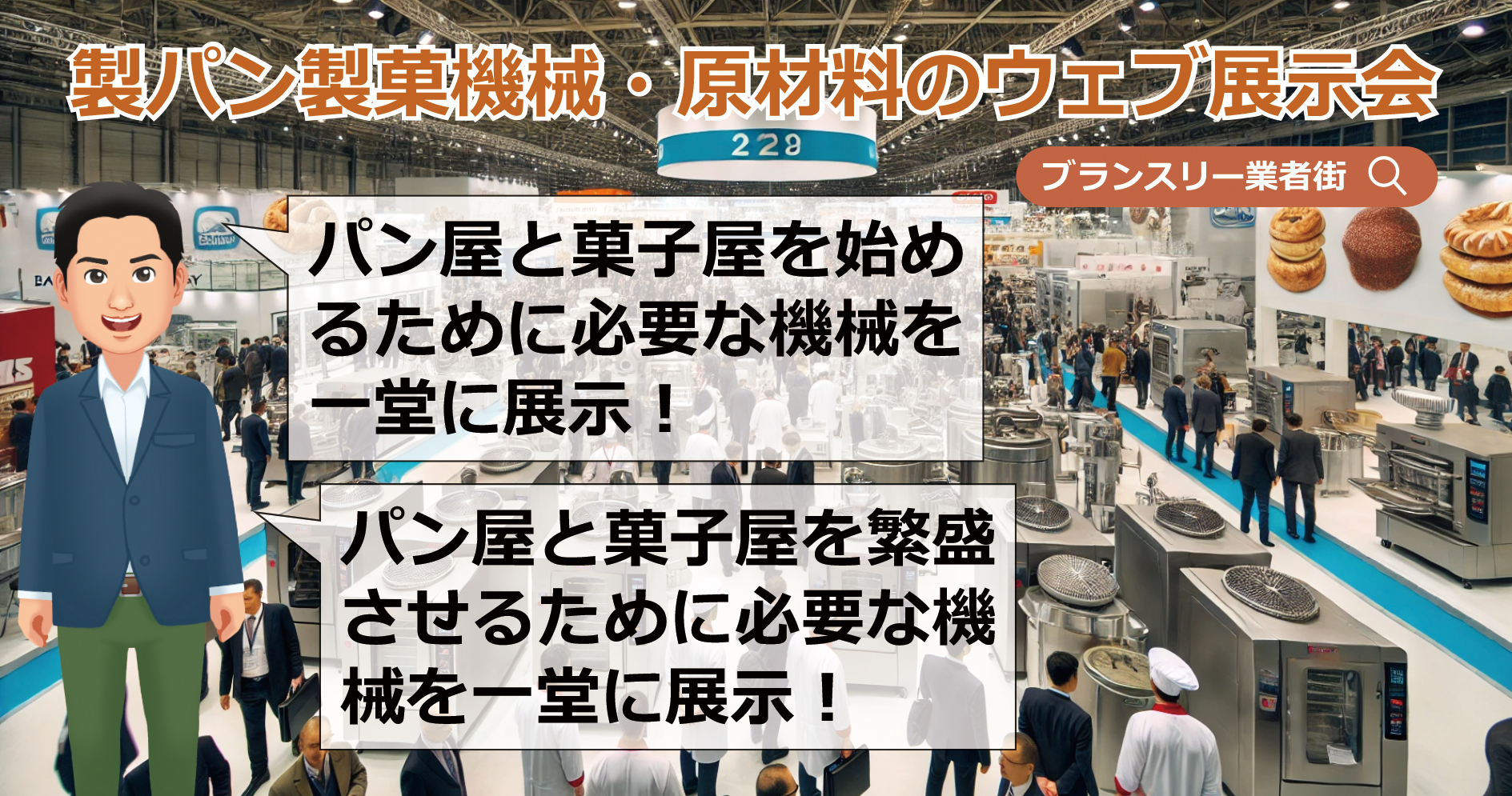
| 流通パンへのシフト傾向も
東京郊外にある某スーパーマーケットのパン売り場。店員が焼きたてパンを陳列するのを待っていたかのように、客が並べたそばから買い物カゴに入れていく。
「どうせ食べるのなら、やはり焼きたてのほうがおいしいので、よく買います。パンだけを買いに来ることはありませんが、焼きあがる時間はいつもだいたい同じ時間なので、その時間に合わせて買い物に来ることはあります」(30代の主婦) パン売り場といっても、大手製パン会社などで製造されたいわゆる袋詰めの流通パンが並んだ売り場ではない。店内で焼いたできたてのパンを並べたインストア・ベーカリーと呼ばれる売り場だ。インストア・ベーカリーとは、スーパー内などでパンを焼き、販売する店のこと。もともと、バブル経済崩壊以降の低迷に悩んだ流通業界が、消費者の選択肢を増やし集客力の向上につなげようと取り入れはじめたのがきっかけで、いまや中規模以上のスーパーなどにはたいてい設けられている。「焼きたて」という付加価値は重要な要素であるという認識がいまや流通業界では常識だ。 たしかに、一時は集客力のアップに貢献したインストア・ベーカリーだが、不況の波は予想以上に高く強かった。2008年のリーマンショック以降、消費者の節約志向は一層高まり、インストア・ベーカリーを含むベーカリー市場は縮小傾向にある。総合マーケティングビジネスの富士経済によれば、2010年度のベーカリー(パン製造小売の業態)の市場は3924億円で前年比6・1%の減少だった。 |

| 冷凍生地の比率アップで拡大路線 | |
|
そんな中、声高々に拡大路線をブチ上げたのが、イオンベーカリー(本社・大阪市)だ。同社は、イオングループのベーカリー事業を担う企業。今年3月には、マイカルグループのインストア・ベーカリー「マイカルカンテボーレ」を吸収合併。旧マイカルグループだったサティ(現イオン)などを含めたグループ内の商業施設にインストア・ベーカリー「カンテボーレ」を展開している。店舗数は2011年3月現在、104店。売上高はおよそ90億円。今後、年20店舗規模で拡大させ、2015年度には200店舗、売上高200~300億円を目指す方針だ。
この強気の戦略の背景には、「焼きたてパンは集客の強力な武器になる」との考えがある。実際、冒頭で紹介した主婦のように、パンが焼きあがる時間に合わせて来店する客もいまなお少なくない。一時ほどのパワーはないとはいえ、インストア・ベーカリーがいまだ有力な集客マシンであることはたしかなようだ。 むろん課題は少なくない。最大のテーマが、「価格」だろう。 「リテールベーカリーの焼きたてパンであっても、隣にホールセールの安価なパンが並んでいるようなスーパー内では、今は100円を切るようなインパクトがなければ消費者に価格的なアピールはできない。ですから、98円均一セールを毎週開催するベーカリーも増えました。とはいえ、ホールセールのパンに比べ、リテールベーカリーのパンは店舗運営にかかる費用、特に人件費がかかります。その分、どうしても価格に響く。いわば『価格との攻めぎあい』がひとつの大きなテーマ」 日本パンコーディネーター協会代表の稲垣智子氏はそう語る。 景気がいっこうに回復しないどころか、新型インフルエンザの流行、猛暑、そして東日本大震災と、消費者の食欲と購買意欲を削ぐ事象がここ数年、立て続けに発生し、世の節約志向に拍車がかかっている。事実、富士経済のレポートよると、インストア・ベーカリーにおいても、菓子パンやカレーパンといった定番商品はまずまず安定しているものの、食パンなどは価格の安い流通パンに消費者が流れる傾向が顕著なようだ。100円均一セールなどを実施して顧客の囲い込みをはかるケースも見られるが、すべての商品を値下げするのはむずかしい。熾烈を極める価格競争に、インストア・ベーカリーはどう挑むのか。 イオンベーカリーが打ち立てた方針が、べイクオフ(冷凍生地を使った製造法)の拡大だ。旧マイカル時代の「カンテボーレ」では、スクラッチ(粉から練り上げて製造する方法)にこだわった商品が特徴のひとつで、ベイクオフは全体の10%にすぎなかった。しかし今後は、その比率を拡大。なおかつ、店の規模によって比率を決めるという。具体的に言うと、売り場と調理場の面積の合計が80~100坪の大型店ではおよそ30%、40坪前後の中型店では約50%、20~30坪の小型店では7割をベイクオフ商品にする方針だ。同社は三重県四日市市と愛知県一宮市に自社工場を有している。これらの工場で冷凍生地を完成品に近い形まで加工し、店内では成形して発酵・焼成だけの作業となる。 |


2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。