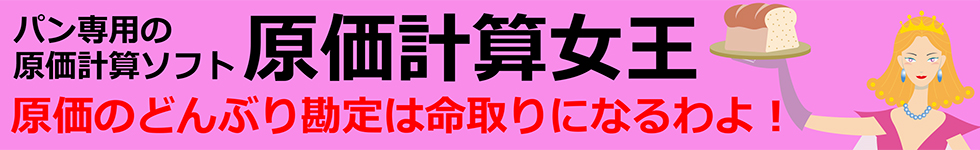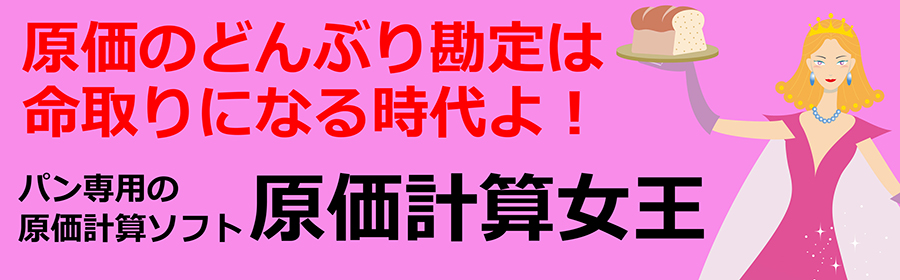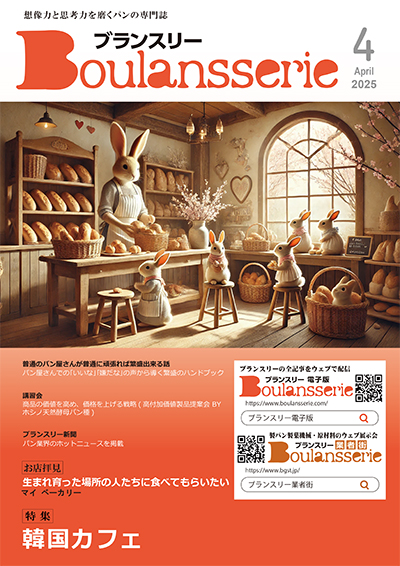記事の閲覧
| <<戻る |
| 実践的ベーカリーマネージメントの基礎知識/2004年8月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| 実践的ベーカリーマネージメントの基礎知識(5)
文・折井英雅
昭和30年に東京農工大学農芸化学科を卒業し、(株)東急フーズ(現サンジェルマン)入社、サンジェルマン開発部長、海外事業部長として国内外約120店舗のインストアベーカリー、レストランベーカリーの企画から開店までをプロデュース。平成3年ハワイ・ディーライトベーカリーでの2年間の社長職の後退社。平成4年から11年まで食糧学院・東京ホテルレストランカレッジ製菓喫茶店経営科(現在、東京栄養食糧専門学校に移管)科長として専門学校の教育に従事。現在はベーカリー会社顧問のほか、名古屋文化短大食生活専攻科講師として製菓製パン理論、フードマネージメント論を講義。所属団体としてはRC・アミカル会副会長、フードシステム研究所主任研究員として「食文化から食マーケティングヘ」の視点から、同研究所の江戸を学ぶ会、新発想開発塾に研究員として参画。 |

| マーケティングリサーチは、目的をはっきりさせて行う
第3章マーケティング活動(続)
第2節 マーケットリサーチ~マーケティングリサーチ 前回のA店の例のように、すでに営業している店でも、「どうも商品が売れなくなった」と考えて、「商品が顧客に合っているのか」を、店の立地から客層を再検討して、考えてみようというのもマーケットリサーチの立派な活動です。 もちろん出店戦略の時に果たして自分の出したい業種業態が予定している物件の場所に合っているかどうか、またその場所に出店したら、どの位の売上があるかの予想をたてるための調査も、重要なマーケットリサーチです。今回はこのマーケットリサーチをどのように認識しらいいのかについて述べ、さらに、店を取り囲む商圏と店の立地の性格についての基礎的な事柄を説明していきます。 1基本的認識 (1)マーケットリサーチとマーケティングリサーチ 厳密にいうならば、マーケットリサーチとマーケティングリサーチは同じ意味ではないといわれます。マーケットリサーチは「現在、市場がどのような状態にあるかの調査」のことで、出店のときの立地調査がこれにあたります。マーケティングリサーチは「市場の状態について知ることにとどまらず、どうアプローチをしていったらよいかまで調査する」ことで、立地の調査をしてからその特性や客層まで考えて、どういうコンセプトの店舗にすべきかまで積極的にリサーチするということです。 ショッピングセンターの開発とか、チェーン店の多店舗展開などを図るようなプロジェクトの時にはオーナー会社が専門の調査会社に出店予定地の情況の調査、いわゆるマーケットリサーチをさせます。そしてオーナー会社は、その報告に基づいて、どのような業種業態にすべきか、商品メニューコンセプトや店舗デザインコンセプトはどうするかなどを決めるために、いわゆるマーケティングリサーチをします。このことからも、マーケットリサーチとマーケティングリサーチの区分ははっきりしています。 しかし小規模のベーカリーでは、商圏や立地の調査をしながら「客層は」「購買動機は」などと考えて、店舗コンセプトの企画も同時にしていると思います。したがって今回の私のベーカリーマネージメントの話ではこの2つを区別せず、マーケティングリサーチで統一します。 (2)マーケティングリサーチの概要 商品開発や出店戦略の企画ではこのリサーチ活動が重要なことはもちろんですが、日常の営業活動においても、関係している市場、消費者(お客さん)、競合相手、取引先等を対象にして、必要とされる種々のデータを様々な手法によって収集、分析、集約し、経営の意思決定をし、発生する問題を解決するための有効的な策を立てる必要があります。こうしたこともマーケティングリサーチ活動そのものです。 これは前回のセンス系統図で説明した「STORY~話題―種々の事柄(物事、情報)を収集、分析、集約して頭の中で有効化できること」と連動したものです。マーケティングリサーチ活動での発想力、企画力の発揮がセンスアップにもなり、またセンスアップした頭でより高い、より深い解決策を導き出すことが出来るのです。 5W1Hで説明すると・・・ マーケティングリサーチの手法の概要をわかりやすく5W1Hで説明します。なお、前回のAベーカリーの天然酵母パンの調査を例にとって考えていきます。 [1]WHO―誰に聞くか 調査の目的によって対象を誰にするかということです。消費財の商品であるパンの場合は消費者(顧客)を対象とする消費者調査が中心となります。 *Aベーカリーでは天然酵母パンの売行調査を店の顧客を対象に行ないました。 [2]WHY―なぜするか 何の理由でするのかをはっきりします。問題意識が明確でないと途中で何を調査しているのかがあいまいになり効果が出てきません。 *Aベーカリーでは新たに発売した天然酵母パンの売行が思わしくなかったので、その原因を調べることにしました。 [3]WHAT―何を目的としてするのか 調査で明らかにすべき課題やテーマを示します。 *Aベーカリーでは天然酵母パンの売行調査で、どこを改良すべきかを明らかにしようと考えました。 [4]WHERE―どこでするか リサーチが対象とするエリアです。大規模になると全国とか、小規模ですと店のある商圏とかになります。 *Aベーカリーでは店に来る顧客を対象にしましたので店舗となります。 [5]WHEN―いつするか リサーチの実施時期と期間です。新商品開発では売出しのタイミングを、店舗出店や改装ではその日程を考慮して決める必要があります。 *Aベーカリーでは新商品の天然酵母パンが売れないので、至急に改良品の再発売をしたいと考え、ただちに調査を1週間することにしました。 [6]HOW―どのようにするのか 調査の方法論です。訪問調査、電話調査、観察調査、グループインタビュー、など種々ありますが、テーマとか費用から最適の方法を考えます。 *Aベーカリーでは店でパンの購入者(天然酵母パンの購入の有無にかかわらず)に、アンケート用紙を渡し、天然酵母パンに対する関心の度合いを聞き、天然酵母パンを買った客にはさらにその評価をしてもらいました。これはアンケート調査です。 調査の結果、天然酵母パンには関心が高く一度は買ってもらったものの、確かに健康には良いようだったが、風味が物足りないという回答が数多くありました。そこで直ちに改良して、蜂蜜入りの天然酵母パンを再発売し、売上増に結びつけました。 |


2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。