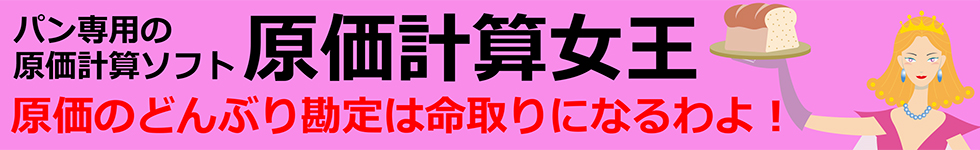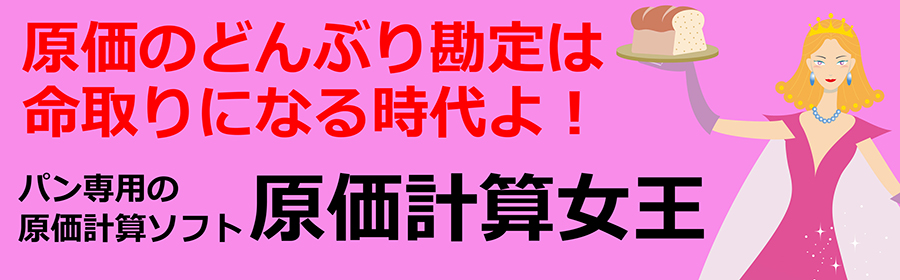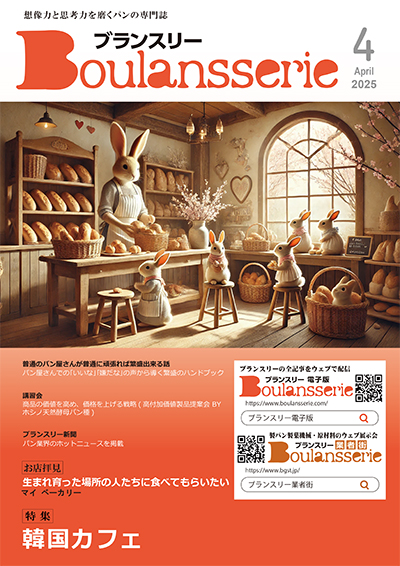記事の閲覧
| <<戻る |
| 生産性よもやま話(13)/2004年7月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| ボトルネックとは生産処理能力の貧弱な部分をさす
[生産性よもやま話]
弘中泰雅 テクノバ(06‐6630‐7812、http://www.technova.ne.jp/) 生産においてボトルネックとは生産処理能力の貧弱な部分をさす。道路でいえば渋滞が起こりやすい狭隘なところに例えられる。 パン工場を指導していると、ボトルネックが放置されていることが多い。多くの場合機械装置そのものではなくて、それらの結合部分であることが多い。 当初からの設計自体が悪いところもあるが、設備の更新で構造が変わったために発生したものも目にする。機械装置そのものであれば、機械メーカーが対応してくれるが、その原因が競合的であればあるほど手に負えなくなる。 たとえばメイキャップの工程で、ラウンダーとオーバーヘッドプルーファーでの連携が悪く生地がダブルになる。 冷却コンベアーと地上の搬送コンベアーの継ぎ目にパンが食い込む、などが見られる。 これらの問題箇所の改善がなされず、仕方ないものとして放置され、結果的に速度を落として分割したり、食い込みやすいものはラックに取ったりして凌いでいる。 そのうちにそれは当然となり、これらが生産性を著しく落としていることすらも忘れてしまう。こんなことが結構起きているが、上記のような対応をすると上級の管理者には分からない。生産のボトルネックの解消、言葉では易しいが、現実には結構大きな問題である。 |
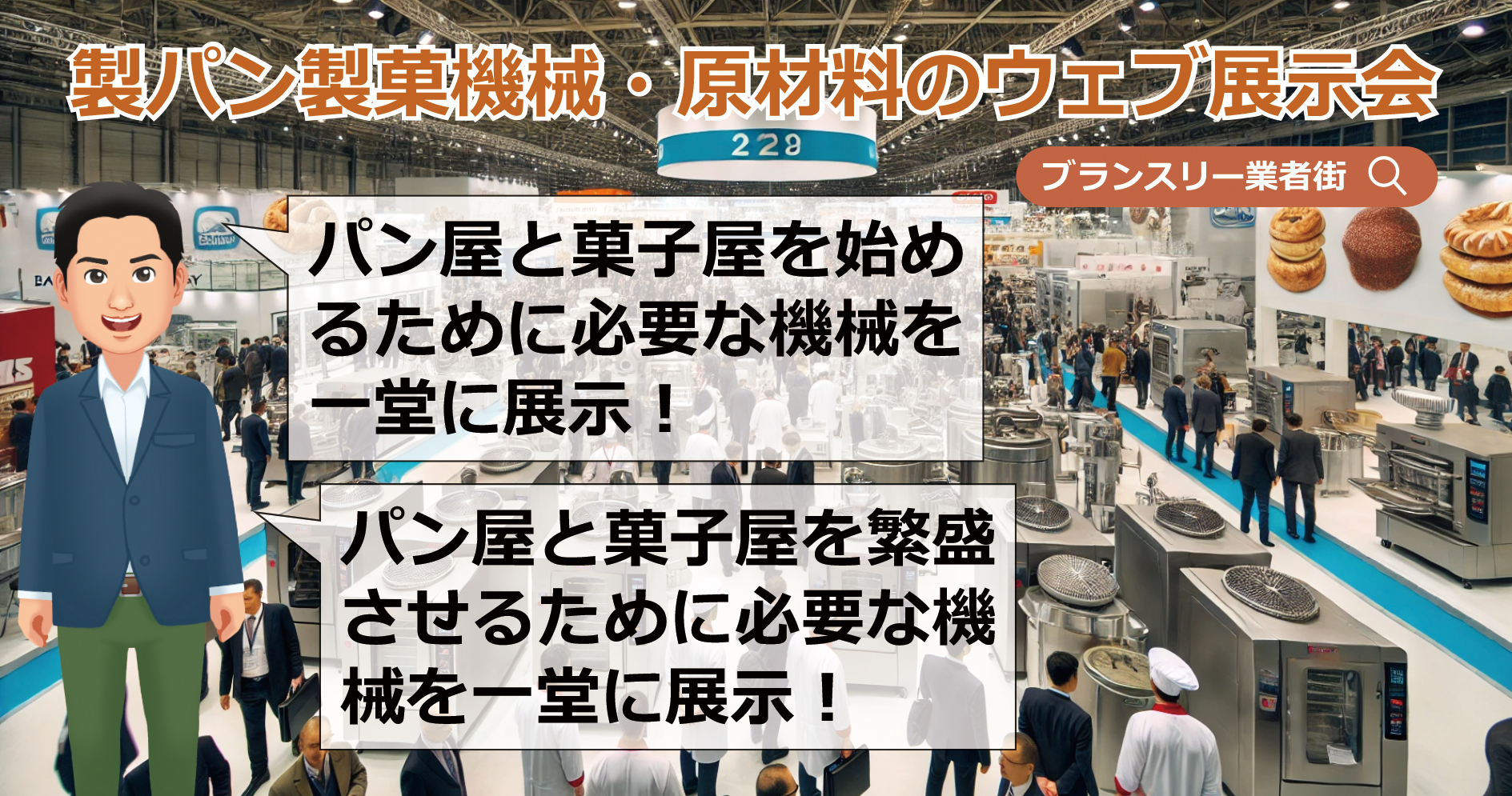



2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。