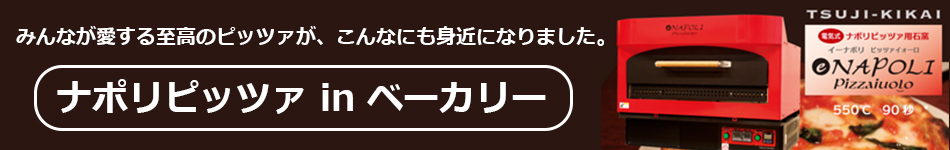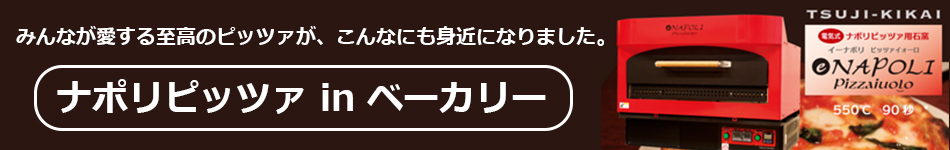6回連載(第5回)
 橋本泰之
橋本泰之 1956年横浜生まれ。新宿の専門学校を卒業後、銀座レストランみかわやに就職。その後センチュリーフーズ、モンタボーなどを経て、1996~2001年、東京製菓学校教師。2001年10月、有限会社レーヴを設立、現在に至る。
うまく焼くには配合を覚えよう今回は焼成について考えていきたいと思います。まず大切なことは、自分の店舗の配合を覚えているかどうかということです。私が店舗にいた時、新人さんにはまず仕込みを教えました。なぜかというと、配合を覚えてほしいからです。いきなり焼成をやらせるのが一般的なようですが、焼成する時に、配合が分かっていた方が理解しやすいし、どうしたらきれいに焼けるか、自分で考えることができます。食パンは、なぜ強火で焼くのか、菓子パンはなぜ上火中心で、短時間で焼くのか、乳製品が入ったパンはなぜ少し温度を下げて焼くのか、などと色々な疑問をもって考えて焼けば、うまく焼けるし、焼成スピードも早くなります。それには、まず配合を覚えることから始めましょう。
乳製品が入ったパンは焼き色が濃いここで、乳製品が入ったパンは焼き色が濃くなることについて、少し話したいと思います。本来パンは、2つの反応から焼き色がつきます。1つは、カラメル反応。これは160℃以上で(一般的にはもっと低い温度でも起こる場合もあります)、糖が反応を起こして焼色が付きます。プリンなどで、カラメルはよく使いますよね。
それからもう一つ、パンにとって大切なメイラード反応があります。正式名はアミノ・カルボニル反応といって、高温で焼くことにより、アミノ酸、たんぱく質、糖が結びついて焼き色がつきます。タンパク質の多い材料が入っている生地は、焼色が濃くなりやすいのです。乳製品には、乳糖が入っています。乳糖はイーストが発酵の段階で分解できずに、そのままパン生地に残ります。だからパンに乳製品を使用すると、焼色がつきやすいのです。また、ドライイーストを使用すると、生イーストの場合よりも焼色が少し赤くなります。これはドライイーストの中の死滅酵母がほとんどタンパク質なので、焼色がつきやすいためです。
なぜ焼き色がつくかを理解して焼くのと、ただ焼いているのでは、大きな違いが出ます。
新人さんには色々な製パンの本があるので、勧めてあげてください。仕事を進めていくと、だんだん理論が大切になってきます。理論だけではパンは作れませんが、パン作りでの様々な現象が理論によってよりよく理解できるので、失敗が少なくなります。
ダンパーを上手に使おうそれでは次に、窯のダンパーの使い方と、焼成温度を設定する出力スイッチの話を、少ししたいと思います。まずダンパーをうまく使用すると、より一層うまく焼き上げることができます。ダンパーは、窯の後ろに小さな穴が空き、窯の中の暖まった空気を外に出す仕組みになっています。その穴からは外気は入って来ません。ここが大切です。窯でのケービングの一番の原因は発酵工程の問題によることが多いのですが(以前発酵について書いた際にも指摘しました)、窯の中に外気が入ってきてしまうことも原因になります。
ダンパーによって、中の温度を外に逃がすことにより、上火が上昇しなくなります。白焼のパンなどを焼く時は、ダンパーは大切だと思ってください。それ以外にも色々な使い方があるので少し考えてみて下さい。

以前、ある講習会で焼成時間を5分、10分などと変えて焼き上げた食パンの断面の写真を見せてもらったことがあります。中の状態を5分、10分と焼成時間ごとに見ていくと、本当に感激ものです。これに触発されて、窯の中でパンが焼けていく過程で、生地温度がどのように上昇していくかを調べてみました。これにより最適な焼成時間と、何分経過するとケービングが起きやすい状態になるかが、理論的にわかりました。参考に表をつけておきましたので見てください。(表1、グラフ1)
グルテンは60℃くらいまで生地を持ち上げます。これがオーブンキックで、この段階まではイーストもまだ炭酸ガスを発生しています。次に、デンプンの方に水分が移行して、α化が始まります。α化は56℃付近から始まります。この時点からパンは、ゲル状になっていきます。ゲル状の時はケービングは起こりません。焼成時間が17分を超えてくると温度が90℃付近に達します。この時点でパンの中心までほぼ火が入ります。あとは表面が焼けるのを待つだけです。この時点からは外気が入るとケービングが起こりやすくなります。
パンが焼き上がっていく過程が、ある程度分かると、白焼パンは初めにオーブンのふたを開けていても大丈夫なことが分かります。ドイツパンは特に内部の温度が大切で、100℃以上まで計れる温度計をパンにさして測ってみるのも参考になると思います。
ソフトなパンを焼く時は焼成温度を、前もって合わせていれば良いのですが、色々なパンを焼いていると、そうもいきません。そんな時にダンパーを開けたままにして、初めの5~6分くらいは、窯のふたも開けたままで焼いてみるのも、ひとつの製パン技術かも知れません。
うまく焼くための方程式を作る最後に焼成の目安をどこに持ってくるかについて、考えてみたいと思います。前回工程表について書きました。工程表通りに進めていくには、仕込の温度が一番大切ですが、窯の焼時間も大切です。いくら工程を組んでも、食パンやフランスパンが、決まった時間で焼成できなければ、どんどん工程は、ずれていきます。
何か目安を作って焼いていくと、いいのではないかと思います。私は前の会社で新規開店の時に、よく窯を担当していたのですが、窯がうまく流れないと工程がすべて止まってしまいます。6取り天板4枚差しの3段の固定窯で、1日100万円以上は生産していました。なぜそんなことができたかというと、ダンパーの使い方を理解していたことと、工程表を最大限に利用していたことが大きかったと思います。すべての製品をそれぞれ何分で焼くか決めていました。それが一番大きなことだと思います。「フランスパンのバゲットなら25分」と決めて焼くのです。
焼成時間を一定にして温度を決める焼減率に関する表を掲載しましたので、参考にしてください(表2a、表2b)。製品を何分で焼くかを決めることが大切です。

窯はメーカーによって、センサーの位置によって、表示温度と実際の窯の中の温度が違います。だからまず基本のパンとして、菓子パン系(砂糖の多いパン)、食パン系(クラムを食べるパンで型焼きのもの)、フランスパン(直火焼きのパン)の3種類について表2a、表2bを参考に、焼いてみると焼成温度が決まります。まず時間を決める、そして焼減率を計って焼き色を確認して、焼成温度を決めるのです。時間は合っていても、焼減率が規定よりも小さいとまだ温度が低い、逆に焼減率が大きいと温度が高い、ということになります。こうしたことを目安に焼成温度を決めてください。焼成時間を一定にしておいて、焼成温度を決めると、色々な店舗へ行って、違う窯を使用してもある程度きれいに焼けます。窯によっては癖がありますが、それはデータをとれば対処できます。
開店の時に窯を設置してもらう際に、水平ラインを合わせて炉床のどの場所でもムラなく焼けるようにしてもらいますが、それでも多少は焼きムラが出てくることもあります。窯の水平ラインを厳密に合わせてもらった上で、奥の方の火を弱くしてもらうと、窯の前後で焼き色が均一になると思います。
以上で今回は終わります、最終回の次回は、冷蔵法について書きたいと思います。