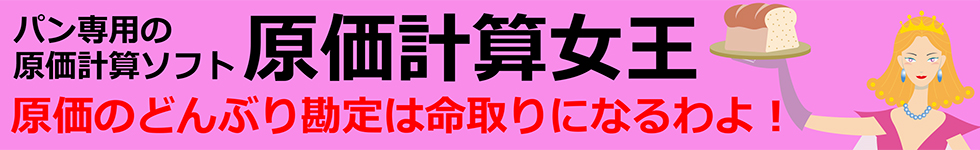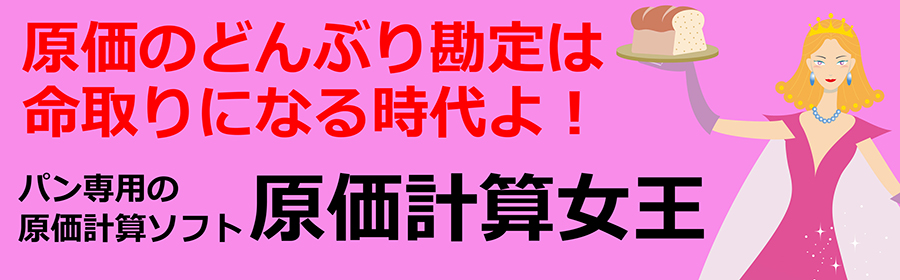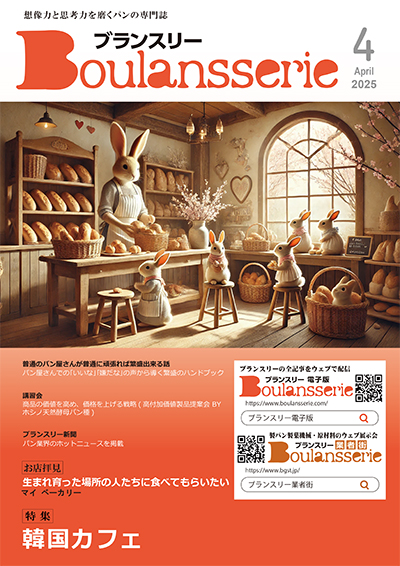記事の閲覧
| <<戻る | 写真をクリックすると拡大写真が見られます。 |
| 講習会/2017年7月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
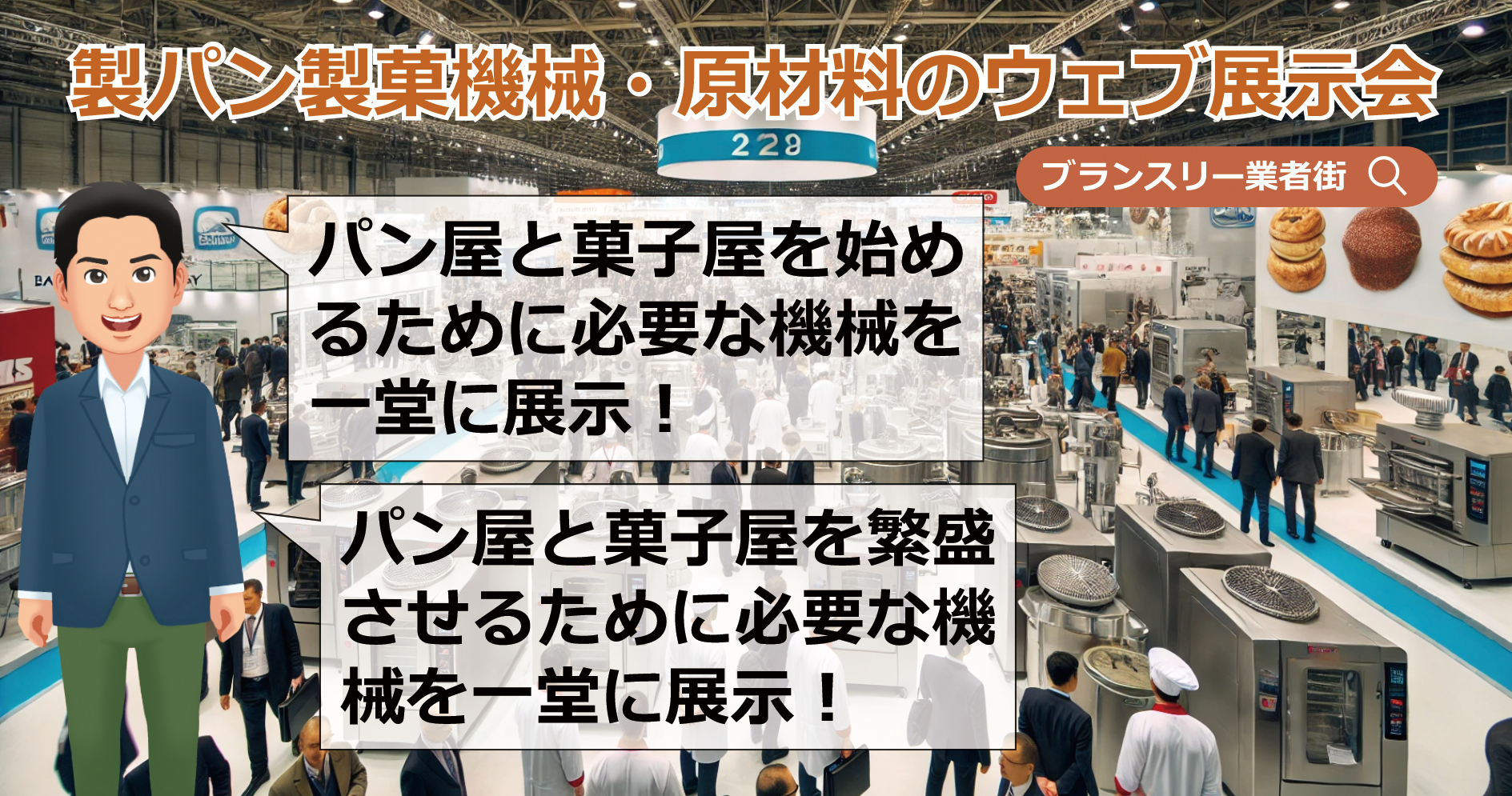
| 小麦粉の甘みを最大限に引き出した食事パンの数々 | |
|
|
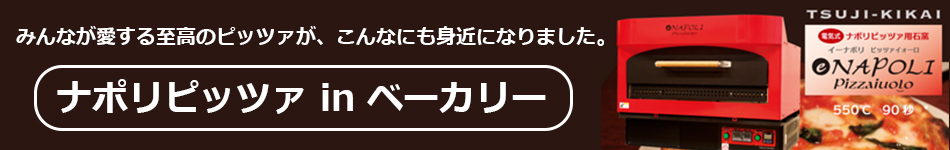
| バゲット・トラディション | |
|
低速だけで優しく生地をこねて、生地を低温で長時間寝かせて作るバゲット。日本では「レトロバゲット」の名前でも親しまれている。
【配合%】 ジェニー(フランスパン用粉、日本製粉)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50 メルベイユ(フランス産小麦粉、日本製粉)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30 グリストミル(石臼挽き小麦粉、日本製粉)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18 FH全粒粉(日本製粉)‥‥‥‥2 塩(天塩)‥‥‥‥‥‥‥‥1・9 インスタントドライイースト青‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0・2 モルト‥‥‥‥‥‥‥‥‥0・2 水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70 パシナージュ(足し水)‥‥‥‥8 【工程】 ミキシング(スパイラルミキサー使用)L5分(オートリーズ2時間)L5分(この間にパシナージュ投入) 捏ね上げ温度‥‥‥‥‥‥25度C フロアタイム‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥30分(パンチ)30分(フロアタイム後、冷蔵庫で一晩休ませる) 分割‥‥‥‥‥‥‥300グラム ベンチタイム‥‥‥‥‥‥‥30分 成形‥‥‥‥バゲット形(写真1) ホイロ‥‥‥30度C70%25~30分 焼成‥‥‥240度C20分(スチーム注入、焼成前にクープを入れる) 安倍講師のコメント フランスでは3種類のバゲットの作り方があります。 まずは、今フランスでもてはやされている「バゲット・ド・トラディション」の作り方で、ミキシングは低速だけで繋いでいく方法です。生地を冷蔵庫で長い時間ねかせて熟成させます。当日仕込みでも長い時間寝かせます。 日本では、「レトロバゲット」として登場し、人気を集めました。 もうひとつは、日本にフランスパンを伝えたレイモン・カルベル氏が考案した製法で、ミキシングの途中に高速ミキシングを加える方法です。メリットは、ボリュームが出ることと、生地が酸化しにくいということです。この製法が今も日本のフランスパンの王道として定着しています。 3つめは、1970年代に流行った、目が詰まった白いバゲットの製法です。高速ミキシングを10分ぐらいかけて、捏ね上がりの生地はある程度硬いものになります。イーストを多めに配合して短時間で作ります。 バゲット・トラディションの製法は、日本では冷蔵法といわれていますが、要するにストレート法です。発酵時間を引っ張るための環境を冷蔵庫に求めているだけであって、発酵の考え方はストレートのバゲットと全く同じです。 フランスパンは、ミキシングはかけない方がいいとよく言われますが、その理由は、生地を必要以上に酸化させると、変なコシがついて悪影響が出るということだと思います。 イーストの量と発酵の温度や時間というのは、バランスの問題なので、単にイーストの量が少なければいいという問題でもありません。 小麦粉が持っているポテンシャルというものもあります。長い時間置いても甘みが出てきて生地が繋がる小麦粉もあれば、長い時間置くと生地が切れてくる小麦粉もあります。 ですので、ミキシングをあまりかけずに長い時間休ませるのが必ずしもいいとは思いません。 イーストが不自然に多いのは、パンの発酵のメカニズムの観点から、澱粉の糖分を食べ過ぎてしまうのでよくないと思いますが、入れたイーストの量と、澱粉を食べていくスピードが問題なので、最終的にパンに残っている糖分がどれくらいあるかということが大事だと思います。 それが小麦粉の自然な甘さを出すということだと思います。 |

| パン ド ベル エポック | |
|
安倍講師の師匠、チェリー・ムニエ氏直伝のパン。吸水がかなり多い素朴な味わいのパン。
【配合%】 メルベイユ(フランス産小麦粉、日本製粉)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50 グリストミル(石臼挽き小麦粉、日本製粉)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 FH全粒粉(日本製粉)‥‥‥‥10 塩(天塩)‥‥‥‥‥‥‥‥2・1 インスタントドライイースト青‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0・2 ルヴァンリキッド‥‥‥‥‥‥30 水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70 パシナージュ(足し水)‥‥‥‥10 パートフェルメンテ(老麺)‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200 【工程】 ミキシング(ツジ・キカイのダブルアームミキサー使用)L約20分(前半に水70%の状態で生地をつくっておいて、後半で足し水をして生地を調整する) 捏ね上げ温度‥‥‥‥‥‥25度C フロアタイム‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥30分(パンチ)50分 分割(写真2=分割時の生地)‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥500グラム ベンチタイム‥‥‥‥‥20~30分 成形‥‥‥‥‥‥俵形(なまこ形) ホイロ‥‥‥30度C70%25~30分 焼成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240度C20分(スチーム注入、焼成前にクープを入れる=写真3) 安倍講師のコメント フランスではアートフェックスミキサー(ダブルアームミキサー)がたくさんあって、生地の温度上昇がなく、限りなく手捏ねに近いミキシングができます。ただ、生地が捏ね上がるまでに時間がかかるという難点があります。最近は加水の多いパンが流行っていますが、加水の多い生地には最も適しているミキサーだと思います。最近注目を集めている「パン・ド・ロデブ」にも向いています。 |

| フランスで学んだエッセンス | |
|
パンの本質はシンプルであること
ヨーロッパではバゲットとかカンパーニュなどが食事用のパンとして食べられていますが、日本では昔から食事用のパンとして、山食やバターロールが食べられてきました。こうした日本の食事パンをさらにシンプルにして作っていけたらと思っています。僕はパンの本質はシンプルさにあると思っています。だから、皆さんにも日本の食事パンをシンプルにして作ってもらいたいと思って、今日の講習会の講師を引き受けました。 当店の店の売上比率は、食パンが22~23%、バゲット類が31~32%ぐらいなので、半分以上は食事用のパンです。オープンしてからほとんど新商品を出していません。それがいいことだとは言いませんが、20代前半の時にあるベーカリーの統括責任者をやっていて、そのときに売上の目標があって、それを達成するために、変化球のパンの新商品ばかりを考えていました。そうしないと、お客さんがリピーターになってくれないのではと考えていました。でもそうしていると永遠に変化球のパンを考え続けなくてはならないし、アイデアだけの変化球のパンが、パンの本質なのかというと、そうではないと思います。 見た目重視から味重視へ あるとき、僕の日本での師匠に「フランスに行ってこい」と言われて、行くことになりました。僕はもともとフランスに行く気はありませんでした。その理由は、フランスの人たちの仕事がそんなに綺麗だとは思えなかったからです。写真で見たフランスのパンも綺麗ではありませんでした。日本の場合は見た目重視で、クープは開いていないと駄目で、若いときにクープがきちんと開いていないパンを作ると、叩かれていました。そういう価値観で育てられた人間が、フランスに行った時に、パンを見るとやはり綺麗ではないんですね。それを見たときに、ここで習いたいという気持ちは湧きませんでした。 しかし、それらのパンを食べると、とてもおいしかったんですね。感動しました。それで、パンの発酵とか味の出し方をここで習わなくてはならないと思いました。最初は3カ月で帰ってくるつもりだったのが、結局5年近く滞在することになりました。そのときに色々な人を紹介してもらったり、いろんなメーカーさんを紹介してもらったりしたのが、今の大きな財産になっています。 自然な甘みがはっきりと分かるパン 僕がフランスパンの味を出すときに一番注意しているのは、一口食べたときに澱粉の甘みがはっきりと感じられるようにするということです。それは炊きたてのご飯の甘みに似ています。そのことをフランスでの師匠のチェリー・ムニエ氏に教えられました。エリック・カイザー氏のバゲットを食べたときも同じ甘みを感じました。フランスのバゲットは、日本バゲットに比べたら綺麗とはいえませんが、自然な甘みがあるんですね。 僕はフランスで学んだパンの甘みを出す方法を、日本の食事パンである食パンやバターロールにも活かして、砂糖の甘さではなく、澱粉の甘みをはっきりと感じられるものを作ろうと常に考えています。 あとは、日本のパンも大事にしたいと思っています。日本でパン屋をやっている以上は、食パンも日本の土壌で育ってきたパンなので、食パンを大事にしたいし、パン業界の先輩達が作り上げてきたあんぱんだとかカレーパンだとか、そういったお菓子パンというのも、大切にしていきたいですね。いまだに売れ続けているわけですから、昔の人が考えたものは素晴らしいと思います。 コンテストの意義は人との出会い 僕は、もともとコンテストには興味がありませんでしたが、僕の師匠のチェリー・ムニエ氏がコンテストに一杯出ていたのがきっかけで、挑戦するようになりました。コンテストのいいところは、同じ目標を持つ色々な国の人たちと出会えることです。そこから得る知識というのはものすごいものがあります。 |
| 欧州のパン食文化を伝えたい | |
|
本物を追求する強い意志を感じた
26歳の時にフランスに行って、初めて本場のバゲットやパン・ド・カンパーニュを食べて、すごく感動したのを覚えています。それ以前の自分が知っていたパンと、全く違う味で、料理とのマッチングが素晴らしく、食事を楽しむというのはこういうことなんだなということが分かりました。その後、パン業界に入りましたが、日本のパンは、私が思っていたのとは少し事情が違って、日本で売れているパンと、ヨーロッパで売れているパンの違いを目の当たりにしました。それから二十数年、ヨーロッパのパン文化を日本に根付かせることを目的に、機械メーカーという立場で仕事をしてきました。今日、講師をお願いした安倍シェフとは、3年前に当社がモンディアル・デュ・パンのスポンサーとなり、そのときの日本代表選手が安倍シェフだったことがきっかけで出会いました。スポンサーとして協力していく中で、安倍シェフといろいろな話ができて、彼の中に、ヨーロッパの食事パンの素晴らしさを感じ、フランスの伝統に重きを置いて、本当にパンが好きで、本物を追求していくんだという強い意思を感じました。それから是非一緒に何かをやっていきたいと思い、今日初めてこのセミナーが実現しました。 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。