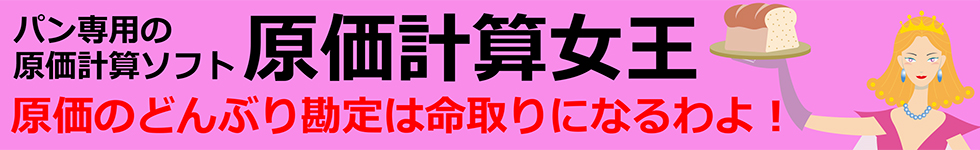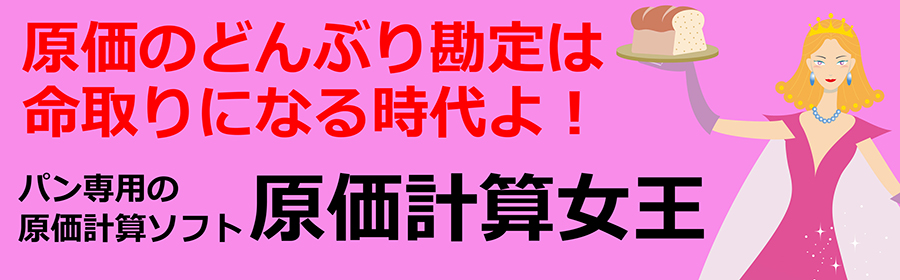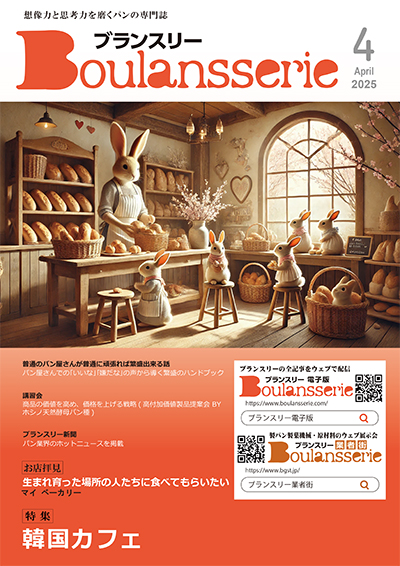記事の閲覧
| <<戻る | 写真をクリックすると拡大写真が見られます。 |
| お店拝見/2016年6月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| お店拝見 特別企画(2)
今回は「お店拝見特別企画」として、リテールベーカリー経営についての4つのテーマを設定して、これまでに掲載されたお店拝見の記事の内容をもとに記事を書いてみました。お店拝見では、これまでおよそ300軒のベーカリーを取材させていただきましたが、改めて記事を読み返してみると、様々なテーマが浮かび上がってきます。
|
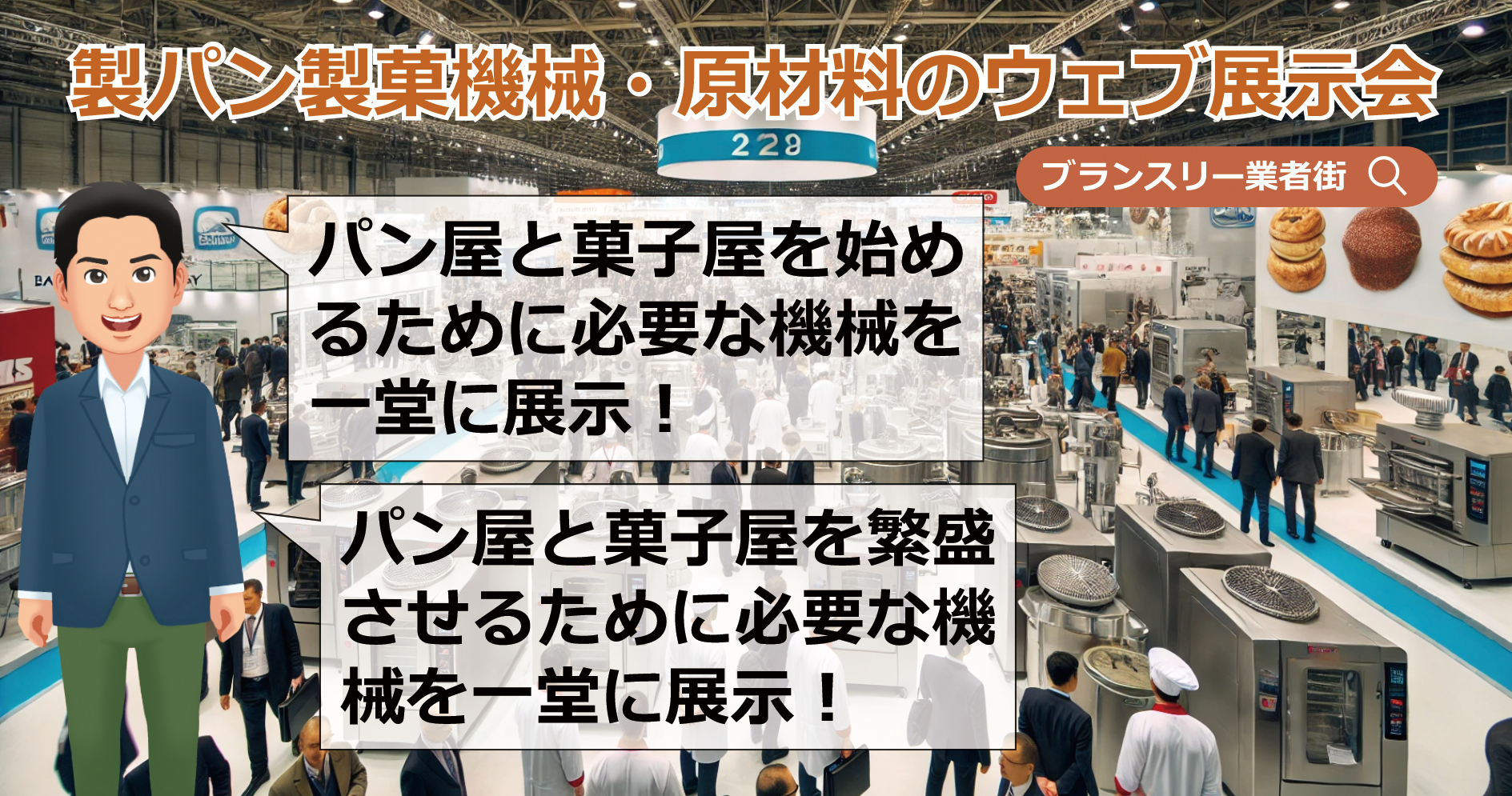

| 焼きたての効果的な演出方法 | |||||||||||||||||||
リテールベーカリーの最大の強みのひとつは、パンを焼きたてで提供できることだろう。客にできる限り焼きたての状態のパンを購入してもらおうと、パンが陳列棚に長い間置かれていることがないように、短時間で売れる量を何回にも分けて焼き上げる工夫をしているベーカリーは多い。例え客が焼きたてを購入して、すぐに焼きたての状態で食べなかったとしても、温もりのあるパンを手にとって購入したという体験自体が、価値があるといえるだろう。 焼きたてのパンのおいしさをできるだけ多く経験してもらおうと、店内にイートインスペースやカフェスペーを設けるリテールベーカリーも多い。 千葉県内に複数の大型ベーカリーを展開するピーターパンの横手和彦社長は、お店拝見2006年2月号の「小麦の郷ピーターパン」の取材で、「あるとき、あるお客様が、パンに手の甲を当てて、『これいつ焼いたパン?』と聞いてきたんですね。つまり焼きたての温もりがないと駄目だということなんです。現在のうちの力では、店に並んでいるすべてのパンを温もりがあるうちにお客様の手に渡すことはできませんが、その理想に近づけるようにできる限りの努力はしています」と話した。 「小麦の郷ピーターパン」は、およそ1200坪の敷地に、大きな2階建てのウッディーな店舗で、石窯と煉瓦づくりの煙突がシンボルだ。庭には、木や花がいっぱいのテラスがあり、横手社長は「自然の温もりを表現したかった」と話した。 パンを焼きたての状態で客の手に渡すことを至上命題とし、ストレート法やオーバーナイトで生地を発酵させる製法など、様々な方法を取り入れることなどにより、少量を頻繁に焼き上げて売り場に出すオペレーションを実践している。 JR中央線・立川駅構内にある「ラ ブランジュリ キィニョン エキュート立川店」(お店拝見2015年10月号に掲載)は、販売スタッフが、 「焼きたてのパン、たくさんご用意しています」と駅利用客に呼びかける。 「たくさんの人が行き交う『駅ナカ』では、声掛けはとても重要です。目の前を歩いている人が、お客様になる可能性があるのですから、声を出して、外に向けてどんどん情報を発信していきます。加えて、試食を出すと、人の集まり方が違いますね。一気に集客できます。夕方の帰宅時などのピーク時にあえて行うのが効果的です」と店長の羽沢周子さんはいう。一度に焼成できるスコーンの量は、60個。1日の焼成回数は約20回に上る。最も売れる冬季は、1500~1600個売れるときもあるので、オーブンが開き次第、次々に焼成していく。 一方、神奈川県藤沢市のベーカリー「プルクワ」(お店拝見2011年11月号に掲載)では、取材時に、「焼きたてです」との声とともに、スタッフがトレイにイングリッシュマフィンを2つのせて運んできた。続いて3分も経たないうちに、「揚げたてです」との声が聞こえ、「カレーパン」が4つ棚に並んだ。その後も焼きたての商品が運ばれてくるが、いずれも2~5個ずつほどと、少量。 「昼の11時半から1時過ぎくらいまでは、外のテラス席などですぐに召し上がる方が多いので、焼きたてを次々とお出ししています。お客様の好みはそれぞれなので、焼きたてのパンに関しては、1種類を多くというより、種類を増やすようにしています」(販売担当の中島友里さん) 同店の社長でシェフの神田淳さんは「焼きたてであることを声に出すか出さないかで、売上げが変わるということを、よくスタッフに言っています」と話す。 | |||||||||||||||||||


2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。