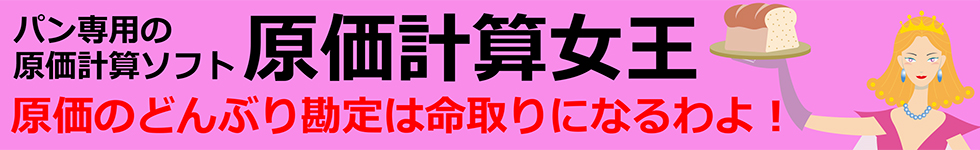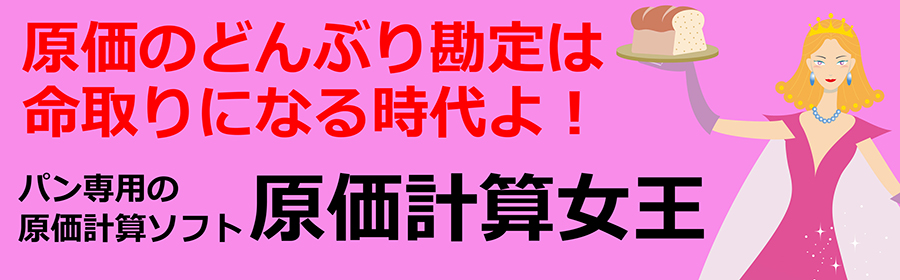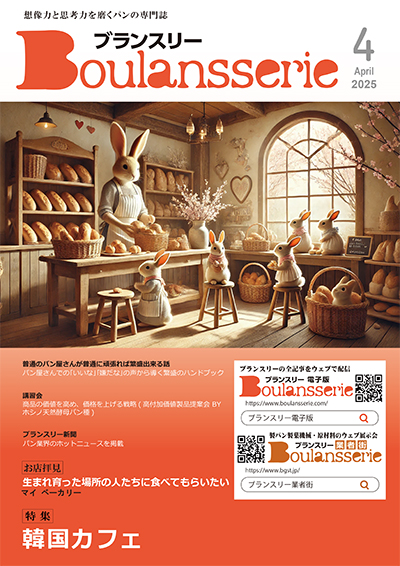記事の閲覧
| <<戻る | 写真をクリックすると拡大写真が見られます。 |
| 特集/2014年8月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
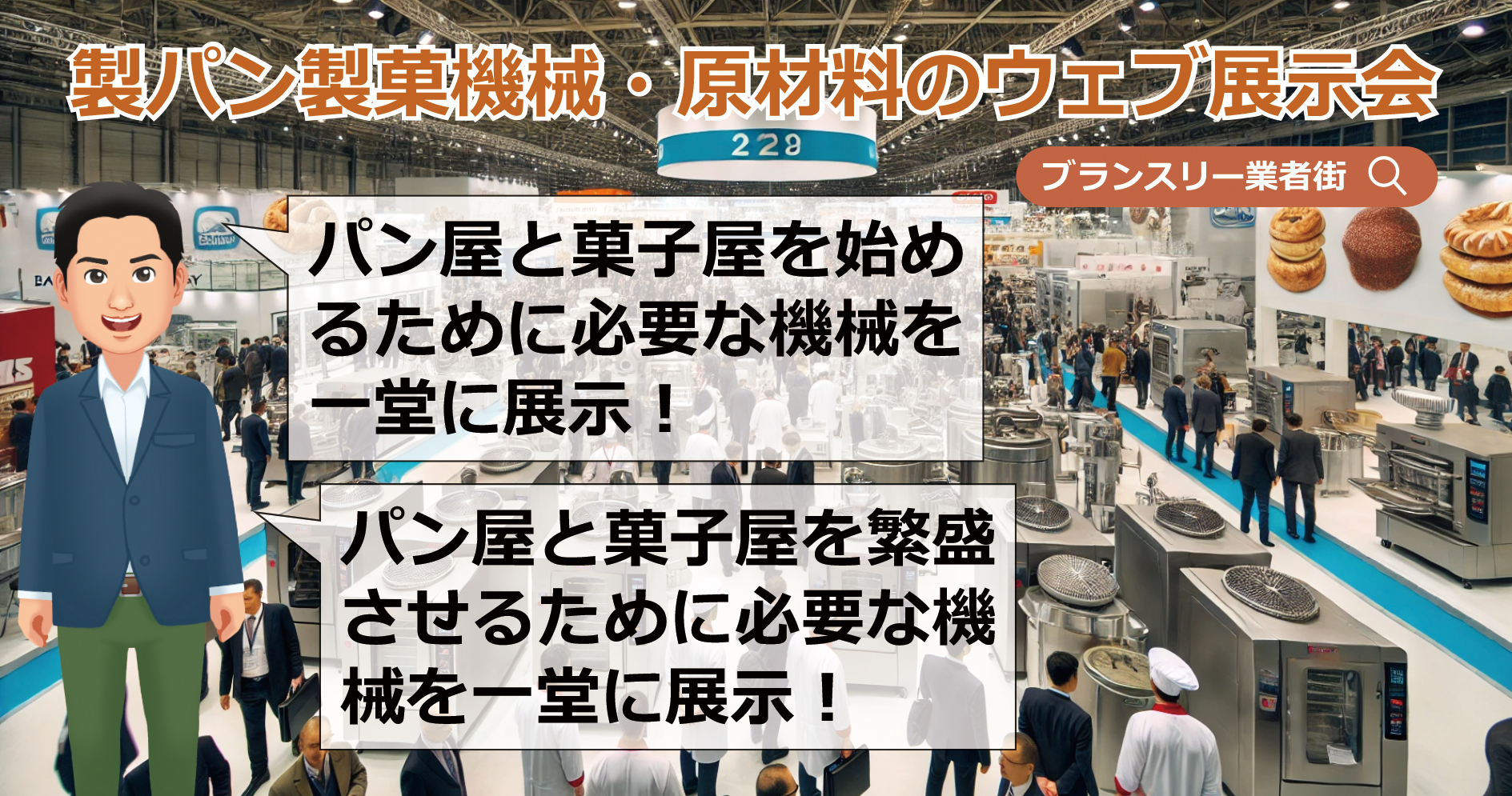
| パンの資格 パンの世界の「案内人」を目指す | |||||||||||||
奥深いパンの世界を迷うことなく案内できる幅広い知識を持った人 パンが趣味の人からパンのプロまで パンシェルジュ検定は、2009年11月の第1回検定以来、2014年3月の第8回までで約2万8300人が受験。運営は日本出版販売(東京・千代田区)が主な実務業務を担うパンシェルジュ検定運営委員会が行っている。「パンシェルジュ」とは、「パン」と「コンシェルジュ」(もてなしをする案内人)を組み合わせた造語で、同委員会は「奥深いパンの世界を迷うことなく案内できる幅広い知識を持った人」と定義している。 入門編である3級から難易度が一番高い1級まであり、出題される問題は、パンの歴史や文化、材料、器具、マナー、衛生環境などの基本的なことについてから、マーケット、トレンドなどを加えたより実践的な内容について、栄養学、未来学、サービス学などを加えた専門的な内容についてまで、多岐にわたっている。告知は公式サイトでの案内のほか、全国の書店でのポスター掲示やリーフレット配布などを実施。また全国に点在する約60のサポーター店のベーカリーが、同様の告知を行うと同時に、合格者への割引サービスも行う。 「パンを作ることや食べることが趣味の人から、パン作りを仕事にする人まで多くの方に、検定受験を楽しんでもらいたいと思っています。公式テキストで勉強すれば合格できる検定です。趣味の範囲でも楽しめるよう、受験料もあまり負担をかけない額にしました」と話すのはパンシェルジュ検定運営事務局である日本出版販売検定事業課の古田亜紀さん。 「気軽に楽しみながらパンの世界に精通でき、パンの専門家のみならず、一般のパン好きの人も勉強しやすいようです。こうした理由から、パンシェルジュ検定は急速に人気が高まってきています」 パンの文化から店鋪運営まで パンシェルジュ検定の問題は、パン教室などの運営で知られるホームメイドクッキング(東京・新宿区)が監修している。問題は全て4択の選択式。楽しんで受けられる要素が強いという。 例えば、まず「明治時代に天皇に献上され、日本を代表するパンとなったのはどのパンか(3級、「コッペパン」「メロンパン」「カレーパン」「あんぱん」から選択、正解=あんぱん)」「2006年~2009年平均でパンの消費量が日本で一番多い人口5万人以上の都市は次のどこか(2級、「京都市」「横浜市」「大阪市」「広島市」から選択、正解=京都市)」といったパンの文化や市場などに関する問題。 一方、「パンの老化を遅らせる働きのあるレシチンは、卵のどの部分に含まれているか(3級、「卵黄」「卵白」「カラザ」「卵殻膜」から選択、正解=卵黄)」、「全く油脂を加えないで作るパンは次のうちどれか(2級、「メロンパン」「フォカッチャ」「バゲット」「ブリオッシュ」から選択、正解=バゲット)」といったパンの基本材料、科学的な部分に関する問題もある。 また「一般にライ麦パンや、オレンジやレモンなど柑橘系のパンに合うとされるワインの種類は何か(2級、「赤ワイン」「白ワイン」「ロゼワイン」「スパークリング」から選択、正解=白ワイン)」「フレンチのコース料理でのマナーで、基本的にパンを食べるタイミングはいつがよいか(3級、「デザートの後」「メインディッシュの後」「スープの後」「前菜の後」から選択、正解=スープの後)」といった食べ合わせやマナーに関する問題も散見される。 1級になると、より専門的な内容となり、店鋪経営や接客面などに関する問題も出題されるようになる。パンの世界を奥深く案内するために必要な多方面の知識が要求されているといえそうだ。 | |||||||||||||

古田さんはこれまで合格者からの反響の声を多数聞いてきたという。その中で多かったのが勉強した内容がパンの販売の仕事で役立っているという声だという。 「お客様とコミュニケーションをとる際に話が膨らみやすいのだそうです」(古田さん) パンの販売では、主にワインやチーズなど他の食材との組み合わせや食べ方提案に関することが役立つことが多いというが、併せてパンの文化や原材料などについての「知識の引き出し」から、ちょっとしたことを話すだけで話題が広がっていくのだという。 1級合格者で、ボランティアで障害を持った子供達とパン作りをしている人がいたというが、「面白がってもらえそうなストーリー的なものがあると教えやすいんです。パンシェルジュの知識がすごく役に立ちました」と言っていたという。 また最近の傾向について「男性の受験者が増えてきていることがありますね」と古田さんは話す。 第1回の頃はほとんどが女性だった受験者も、回を重ねるごとに男性も増え、第8回では第1回の2倍ほどにもなったという。男性の場合、将来自分の店を持ち、自分の作ったパンを提案したいなど明確な目標を持っている場合が多いそうだ。実際事務局のほうで受験者の男子を何人か取材したところ、パンに関わる仕事をしている人が多かったのだという。 「団体受験の枠があるのですが、著名なベーカリー専門店の方達が揃って受けられたりしています。ベーカリーなどの社員教育として、パンシェルジュを利用していただけると嬉しいです」(古田さん) 実は、運営委員会が受験者にとったアンケートでは、日常的に自宅でパンを作る人の割合(「頻繁に作る」「時々作る」の回答)は半分近くに上ったという。 「自分がパンを作って楽しむだけだった人が、その世界を他の人にも伝えられるようになりたいと考え始めているようです。そこにパンシェルジュ検定の需要があるのかも知れません」(古田さん) 3者で「ウィン・ウィン」の関係 パンシェルジュ検定では受験者とオフィシャルサポーター、そして事務局である運営委員会の3者の関係を大切にしているという。受験者へは、フェイスブックやブログ、ツイッターなどの公式サイトから情報発信している。 「運営側としてはとにかくパンの文化を楽しむ人を増やしていきたいですね。そのためサポーター店は随時公式サイト上で募集していますし、今後も増やしていきたいと思っています」(古田さん) 現在、パンシェルジュ検定にはベーカリーやパン教室などから構成される44のオフィシャルサポーターと19のサポーターが全国各地にいる。サポーターに関する情報はパンシェルジュ検定公式サイトやブログに掲載。ネットを使用した相互コミュニケーションの活性化を目指している。また、検定以外にもオリジナル商品などを企画し、受験者にパンを楽しんでもらっている。第8回検定開催時には、サポーター店で、東京・三宿のベーカリー「シニフィアンシニフィエ」の志賀勝栄シェフが厳選した小麦粉とオリジナルレシピのセットを公式サイトで販売し好評だったという。 パンシェルジュ検定は、単に試験を実施して合格者を出すだけでなく、その中で作られる様々なコミュニティーで身近なパン文化を盛り上げてもいるのだ。 「運営委員会、サポーター店、受験者の3者が相互に『ウィン・ウィン』の関係を作ることが理想です。それが結果的に『日々の生活をもう1ランクアップさせ楽しみたい』という気持ちに応えられるものになればと思っています」(古田さん) 資格名:パンシェルジュ検定 主催:パンシェルジュ検定運営委員会 協力:?ホームメイドクッキング 開催頻度:年2回 受験会場:全国8エリア 受験料:3級4200円(3990円)、2級5460円(5145円)、1級7350円(6930円)カッコ内は団体割引料金、その他3級と2級の併願割引もある 問い合わせ:検定運営事務局(電話03-3233-4808) | ||||||||||


|
<
|
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。