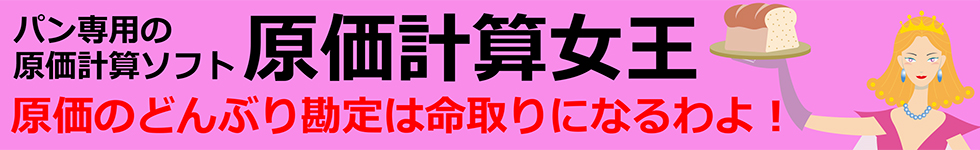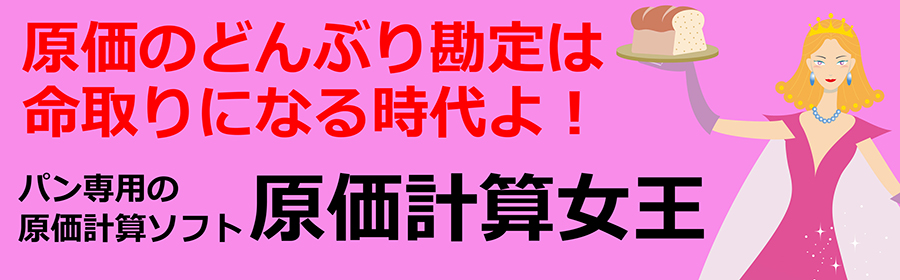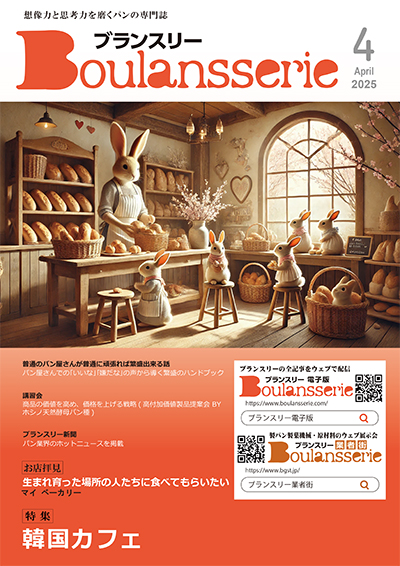記事の閲覧
| <<戻る | 写真をクリックすると拡大写真が見られます。 |
| インタビュー/2011年8月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| これからのパン職人は、グローバルな視点を持て‐倉田博和社長に聞く デイジイ本店・埼玉県川口市弥平2-9-17、電話048-227-6060 | |
|
埼玉県川口市に本店があるデイジイは、埼玉県内に7店舗を展開する年商12億円のリテールベーカリーだ。倉田博和社長は、技術力も販売力も持ち合わせた優れたパン職人だが、会社の規模が大きくなった今、会社を組織としてどうやって運営していくかに心を砕いている。また、ドイツ・パン菓子勉強会の会長を務め、後進の指導に当たるなど、業界発展のための活動にも多くの時間を割いている。今回の取材の中で、「カリスマパン職人」として繁盛店を作り上げ、それを企業として組織化し、さらには、今後のパン業界が進むべき道を真剣に考える倉田氏の姿が浮かび上がった。
|

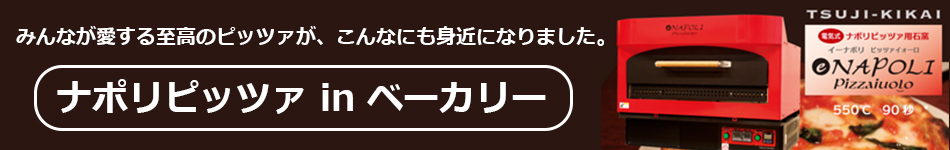
| 売上が上がるときは、いくつかの壁がある | ||||||||||
倉田 売上が上がっていくときには、壁がいくつかあるんですよ。例えば6万から10万の壁とか、10万から15万の壁とか、そんな感じです。20万から30万の壁もあります。今でも覚えていますが、初めて日商30万円をクリアしたのはオープン3年目の12月31日でした。「やっとここまで来たか」とそのときは涙が出ました。 ―――最初の6万円から10万円の壁はどんな感じでしたか? 倉田 6万までは1人ですべてできるんです。でも10万売るには、人を使わなくてはなりません。1人だと当然1人の仕事しかできませんが、2人だと「1+1=2」ではなく、3にも4にもなるんですね。 ―――10万から15万の壁はどうでしたか? 倉田 品物が回転し出すということですね。それまでは、結局朝焼いて終わりだったんです。それが同じ商品を2回、3回と焼くようになってくるんです。そうすると、「焼きたて」や「揚げたて」というイメージが出てきて、お客さんがお客さんを呼ぶという雰囲気になってくるんです。だから、リテールベーカリーの場合、6万でも一人で作って販売のパートさん数人でまわせば成り立ちますが、15万売れれば、さらに上に向かって動き出し、店が潤う方向に進んでいくんですよ。 ―――20万円から30万円の壁はどうでしたか? 倉田 かなり忙しい状態が常態化する中で、お客さんを飽きさせないように、品揃えをさらに充実させ、お客さんが何を望んでいるかをチェックして、それにきちんと応えていかなくてはなりません。ここまでくれば、商売もかなり面白くなってきて、やることがすべてうまくいくみたいな感じになってきます。 ここで一番大切なのは、品揃えを充実させることと、商品の品質をいかにして維持していくかということになってきます。そして、ここまでは、オーナーがすべて直接管理できます。しかし、これ以上になってきて、2店舗目、3店舗目を出すとなると、オーナーがすべて直接管理できなくなってくるので、人の管理も組織論になってきますね。 ―――今は7店舗を展開する年商12億円の企業になったわけですが、倉田さんの仕事の内容もだいぶ変わったのではないですか? 倉田 私は職人ですから、工房に入っていたいという気持ちはあるんですが、どうしても人の管理や人材教育ということになってくるんです。会社が大きくなってくると、労働条件の問題や、著作権の問題など、小規模でやっていたときにはあまり問題にならなかったことが問題になってきます。でもそれが本来あるべき姿だと思うので、特に労働条件の改善には熱心に取り組んできました。 ―――以前と比べたら労働条件がだいぶよくなったということですね。 倉田 昔は、朝3時、4時に出てきて夜遅くまで働いても、自分が店を出すという目的があって、成功事例も多くて、誰でも店を出していい思いができたんですね。 でも今は、成功事例も少ないし、10年間修業しても、自分の店が持てるとは限らないし、きつい仕事をして10年たっても何もないとなったら、「失われた10年をどうしてくれるんだ」ということになってしまいます。 だから、「きちんとした労働環境で働いて、給料をもらって、それなりの生活ができる」という状況にしてあげなければならないんです。そうするためには、生産性を上げなければならないのですが、生産性を上げるためには、製法や段取りを、極限にまで追及しなければなりません。当然、社員1人ひとりの作業スピードも早くしなければなりません。そのためには、自分たちの都合よりお客さんの都合を優先させることが大事になってきます。例えば、特注が入ったときに、従業員としては前の日に作った方が楽なんですが、お客さんの立場からしたら、納品日の朝焼いた劣化のないパンを食べたいはずなので、そちらの都合を優先させないといけないんですね。それを何とか実現させようと段取りや製法をいろいろと考えるから、そこに創意工夫が生まれ、進歩があるわけです。 ―――製法については、どんな工夫をされていますか? 倉田 成形してからのホイロ温度を15度Cにして、焼く前になったらホイロの温度を例えば32度Cにしてやれば、10分でふいて焼ける状態になります。15度Cだと1日の間だったら、無理なく引っぱることができます。 あとは、冷蔵中種法を導入しています。中種を18時間から48時間熟成させて、本捏ね後20分で分割・成形し、ホイロをとって焼成です。だからうちは、店の開店時間の2時間前出勤で十分いけるんです。あとは、ストレート法や生地玉冷蔵、全量中種法などいろいろな製法を組み合わせて1日のオペレーションを組んでいくわけです。 | ||||||||||

| 数字で縛りすぎると創意工夫が出てこない
―――7店舗も展開していると、全体をきちんと見ていくのは大変ですね。
倉田 きちんと数字で見るようにしています。でも私は職人なので、あまりにも数字を見すぎてしまうと、いいものが作れないと思っています。数字で管理し過ぎてしまうと、社員がお客さんを見られなくなってしまうのではないかと思っています。だから私は数字は、客数、売上、利益、原材料費、人件費だけを見ています。数字で社員を縛ってしまうと、社員の創意工夫が出てこなくなって、かえってマイナスになるのではないかと考えています。 ―――ベーカリー経営で最も大切なのは何だと思いますか? 倉田 フランスパンやドイツパンをうまく作るのも技術ですが、人をポジションにはめてうまく頑張ってもらうのも技術なんですよ。そして人がちょっと弱っていたら、それをフォローして、やる気を取り戻せるように仕向けるのも技術なんです。でも人それぞれ、生まれも育ちも違うし、「右向け右」でできるものではなく、1人ひとりと向き合わないとだめなんですね。「右向け右」といっても、上を向いている人もいれば、下を向いている人もいるわけですから。そうしたことを考慮しながら人を組んでいくことが大事なんです。うちは、毎月社員にレポートを書かせています。来月の目標と、今月の反省、自分の意見の3つを書いて提出させています。目安箱みたいなもので、直接上司にはいえないような悩みも書かせています。そして悩みを抱えている社員のところには、私が直接行って相談にのるようにしています。 ―――倉田さんが考える理想的なリーダー像とは? 倉田 頭に立つ人間は、素直じゃないとだめですね。自分の力の無さを隠すために威張ってしまう人間っているじゃないですか。でも、本当に力のある人間は、威張らなくても人はついてくるんですよ。店長は部下と共に成長していこうという姿勢の人じゃないと、勤まらないですね。 |

| 世界に目を向けて仕事をする
―――倉田さんの今の課題は何ですか?
倉田 私の今の悩みは、週休2日になり、夏休みもたっぷりとれるようになって、労働条件が整ったのはいいのですが、そうすると追い詰められることがなくなり、本当の技術者が出てきづらくなっていることですね。それが本当に残念です。私たちの修業時代は、本当に追い詰められて苦労して、どうやったら早くなるんだろうとか、どうやったらおいしいものが作れるんだろうとか、必死で考えながら仕事をしたものです。今の時代は、追い込まれる状況がなくなってしまったので、本物の職人が育ちづらい環境になってしまいました。 ―――倉田さんは中国や韓国で技術指導を積極的に行っていますよね。 倉田 閉塞感が充満し、先行きも見えないし、この国はいったいどうなるのだろうか、日本でこのままやっていっても先があるのだろうかと、不安になっている若い人たちはたくさんいると思います。そうすると、どこで飯を食おうかということになれば、やっぱり海外に目を向けて頑張ろう、という話になってくるんです。私が海外で一生懸命活動しているのには、そんな事情もあるんですよ。 9月には、上海で私がコンサルティングをしている店がオープンします。中国では、日本の技術者が切実に求められていますから、日本の職人にとってはチャンスなんですよ。考えてみれば、世界で4人に1人は中国人です。日本、韓国、東南アジア諸国の人たちも入れれば、アジア人の人口はとてつもなく多いわけで、その市場で日本のパンのノウハウが必要とされるのであれば、惜しみなく提供したいと思っています。 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。