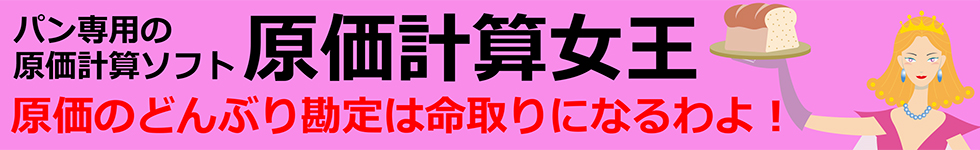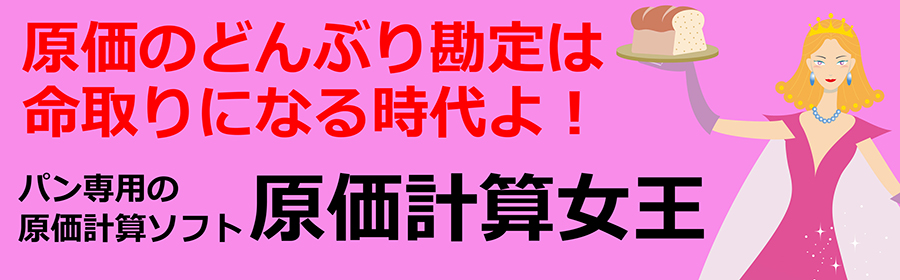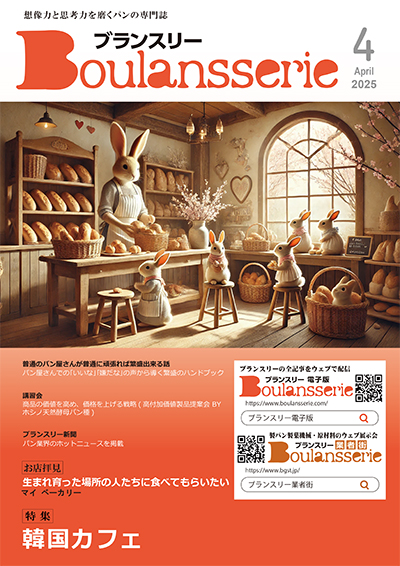記事の閲覧
| <<戻る |
| 特集/2003年7月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| 独立して、何が変わったか
「パン職人の道を志したからには、いつかは自分の店を持ちたい」と考える人は多い。しかし、独立という目標を達成するためには、クリアしなければならない事柄が多い。
リテールベーカリーのオーナー4人に、独立までの道筋や独立後の変化などについて、取材した。 |
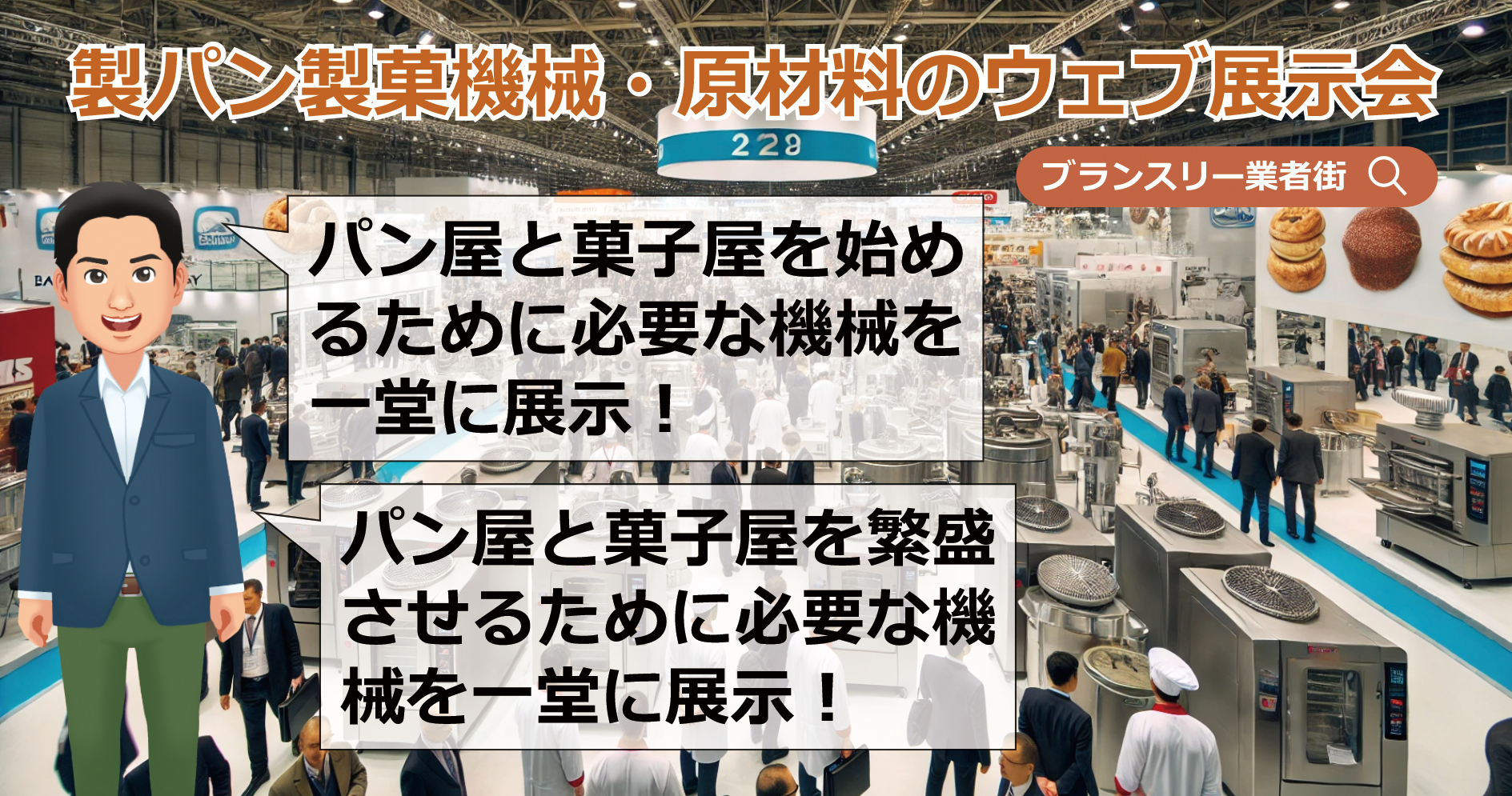
| 独立の期限を決めた方がいい - 鈴木恒美さん ベルウッド
独立への強い思い目的意識を持つ
「独立しようと強く思っていれば、普段の行動も違ってくるはずです」。こう話すのは、東京・足立区でベーカリーを営む鈴木恒美さんだ。店名は、ベルウッド。天然酵母のパンを地道に作り続けるベーカリーだ。「『3年後に独立する』『35歳までに独立する』などと期限を決めることが大事だと思います。『ゆくゆくは独立する』では結局伸び伸びになってしまい、気がついたらもう50歳近かった、ということになってしまいますから」 鈴木さんは19歳のときにある有名ベーカリーに入った。独立するという目的は最初からはっきりしていた。3年間で一通りの技術を身につける気持ちで頑張った。3年後、退社。次に小さなリテールベーカリー4件で1年ずつ働いた。 「最初の3年間は、パンを作ることだけに集中しました。しかし、それだけでは不安に感じたので、小さなベーカリーばかり、4店でさらに働きました。最初の3年間は分業体制になっていたので、パンを作ることはみっちりとできたのですが、商品開発や販売などについては、ほとんどかかわりませんでしたから」。 土地さえあれば貸してくれた 父親が、東京・足立区で居酒屋を営んでいた。鈴木さんはそこでベーカリーを開こうと決めていた。具体的に独立に向けて動き出したのは、オープンの7カ月前だった。「下の子供が幼稚園に入り、ある程度手が離れたのがきっかけでした。実際に始めるとなると、やはり妻の力が必要ですから。実際に動き出すと、どんどん事は運ぶものです」と鈴木さんは振り返る。 パンの機械や材料の調達などについては、「独立するつもりでベーカリーで働いていれば、それなりのパイプはできるものです。店を営業できる体制に持っていくのは、それほど大変ではなかったと思います」(鈴木さん)。 開業資金については「私が開業したころは、まだ、土地さえあればお金を貸してくれる時代でした」。 ベルウッドのパンの品揃えは、開業当初と現在とではかなり違う。最初は、3年間パン職人として働いた有名ベーカリーで覚えたハード系やデニッシュなどが主体だった。 しかし、客の好みに合わせてどんどん変わっていった。 情報に敏感になった独立は少数派 鈴木さんは「独立する前と、後で何が違うかといえば、やはりどうしたら売れるパンが作れるかを本気で考えるようになったことです。使われていたときも考えてはいましたが、商品開発なんかは、専門の部門があったし、決められた通りに作るだけで精一杯という感じでした。そうすると気づかないうちに発想が沸いてこなくなってしまうんですよ」。 独立してからは、情報にも敏感になった。いろいろな情報を常に自分の中の引出しにしまっておくと、ふとしたことで、アイデアが浮かんでくるのだという。 ただ、鈴木さんによると、自分の店を持って、独立できる人は少ないという。「昔いっしょに仕事をしていた仲間が現在どうしているかと考えると、独立した人はかなり少ないかも知れません。途中で脱落した人もいます。会社に残って、指導的立場で頑張っている人もいます。いろいろなベーカリーを渡り歩いている人もいます」。 「私の経験からいえば、いざとなると人間は思ったよりはるかに大きな力を発揮するものです。これは実感です」 鈴木さんは最後にそういった。 人間、いざとなれば、物凄い力を発揮するものだ。 |

| わずか一カ月で店を立ち上げた - 山﨑雄二さん パンリコ
多くの人に助けられた
「人に生かされている。独立してから本当にそう思うようになりました」 大阪市平野区のベーカリー、パンリコの山﨑雄二さんはこう話す。独立してから、多くの困難に遭遇したが、そのたびに親身になってアドバイスしてくれる人がいた。「しんどくなると、なぜかタイミングよく電話が来たりするんですよ。それでどれだけ救われたかわかりません。人間、1人では何も出来ないわけで、感謝の念が自然にこみ上げてきます」 山﨑さんは、2000年5月19日にパンリコをオープンした。それまで働いていたベーカリーを同年4月20日に退社、わずか1カ月でオープンにまでこぎつけた。 独立する前に働いていたベーカリーのオーナーには、1年で独立したい、と伝えてあった。そのオーナーは、「いい店舗物件があったら紹介してほしい」と複数の人に当たりをつけてくれた。 製パン材料問屋、OYTフーズの藤田耕一社長から居抜き物件の紹介があり、検討を重ねた結果、そこで開業することになった。物件の引渡しを受けたのが5月1日で、5月19日のオープン、という強行軍だった。 開業資金はおよそ700万円。そのうち500万円は国民金融公庫から借り入れた。とにかくお金をかけないことを心掛けた。藤田社長が、お金を掛けないで済むように尽力してくれた。 「物件の引渡しを受けてから10日間ぐらいは、毎日朝から夜遅くまで、掃除をしていました」と山﨑さんは振り返る。「床には粉が層になって溜まっているし、フライヤーの周りは油がこびりついているし、本当に大変でした。壁もかなり汚れていたので、ひたすら磨きました」 居抜き物件ではあったが、機械設備はかなり古く、台下冷蔵庫、フリーザー、ホイロ以外は、入れ替えなければならなかった。 藤田社長が、廃業したベーカリーの機械一式を確保してくれた。ただ同然の値段だった。機械の搬入もトラックとフォークリフトをレンタルで調達して行った。 自ら内装工事も行った 内装工事も業者数人と山﨑さん自らも手伝って行った。基本的に現状の状態を生かして、ポイントに手を加えるという手法をとった。 「平台を変えると、効果的に店の雰囲気が変わると思いました。以前のオーナーがやられていたときは、平台を置いていなかったようなのですが、私は家具調の台を売り場中央に置きました。売り場にボリュームが出て、かなり変わりました」と山﨑さん。 ポップ作りにも力を入れた。作り手の思いが伝わるようにと、すべて手書きでていねいに作った。ポップは物件の引渡しを受ける前にすべて作っておいた。 山﨑さんは「オープンにこぎつけるまでの間、何が最も大変でしたか」との質問に対して「スタッフの確保です」と答える。知り合いのパン職人に2カ月間手伝ってもらい、業者に紹介してもらったヘルプの職人には1年間働いてもらった。販売スタッフについては、以前のオーナーのもとで働いていたスタッフの何人かがそのまま残ることになった。さらに4人を公募した。山﨑さんは「とにかく元気で明るいこと、という基準で選ぶしかありませんでした」と振り返る。 オープンに合わせて、住居も店の近くに引っ越した。住居の引越しは、ちさ夫人が担当。子供の保育園の手続きなども同夫人が行った。同夫人は、オープン数日前に店に入った。 山﨑さんは「出店するに当たって、家のことはすべて妻に任せました。その分、自分は店のことに集中できました」。 しんどくなると、なぜかタイミングよく、誰かから電話がかかってきた。 |

| 自分で作って販売したかった - 磯部政利さん アン・トゥ・タン
最初は共同経営の形だった
東京・品川区のベーカリー、アン・トゥ・タンは、オーナーの磯部政利さんが、フランスのある農場で食べたカンパーニュの味に感動し、その味を日本の人たちにも味わってもらおうと、およそ2年半前にオープンしたベーカリーだ。 磯部さんは、水産関係の大学を卒業、ベーカリーオーナーとしては、変わり種だ。築地の水産関係の会社に勤めていたが、自分で作ったものを自分で販売したいと思い、パン職人になることを決意した。 それまで勤めていた会社を辞め、あるベーカリーに見習いとして入った。 その後もある大手リテールベーカリーなどでパン職人として修業を積んだ。 最初に店を持ったのは、1999年秋。大学時代の友人との共同経営という形だった。フランスの農場について教えてくれたのがその友人だった。 「彼はある自動車会社に勤めていたのですが、もっとやりがいのある仕事をしたいと思っていたようです。私は、自分の店を持つことが目標でしたが、いきなり1人で店を出すのは大変だと思っていました」(磯部さん) フランスの農場で味わったカンパーニュは2人共通の体験だった。しかし、共同経営は難しかった。経営方針で意見の食い違いが目立つようになり、磯部さんは1年後、手を引くことになった。 独立前には味わったことのない充実感 2001年1月、磯部さんは東京・品川区に、今度は単独で、アン・トゥ・タンをオープン。共同経営で培ったノウハウを基本的には継承しながらも、より磯部さんらしい店作りに努めた。 フランスで食べたカンパーニュも、さらに研究を重ねて、磯部さん流に作り変えた。商品名は「ブラン」。 売り場の中央に置いた石臼で国産小麦を挽いて全粒粉を作り、同商品の材料として使用している。 「いまは、全責任を自分で負わなければなりません。何があってもすべて自分に降りかかってくるわけです。自分が休んだら、店は開けられません。そう考えるときついと思うこともあります。労働時間もかなり長いですし、肉体的にも楽ではありません。しかし、使われているときにはまったく味わえなかった充実感があります」 さらに「共同経営で得たものはかなり大きかったと思います」とも。 磯部さんが今、最も大変だと感じているのは、スタッフの能力をどうやって引き出すかだ。 現在、製造補助や販売のパートスタッフを雇っている。 「どこまでフォローして、どこからは突き放すべきなのか、などいろいろと悩むことは多いですね」と磯部さんはいう。 使われているときにはまったく味わえなかった充実感がある。 |

| バイクで、店舗を探しまくった - 林春二さん アルル
開業資金は当時のお金で170万円
「独立するには裏づけとなる資金が必要です。自分でこつこつと貯めたお金なら、機械ひとつ買うのにも相当神経を使うはず。いろいろなものを見る目が厳しくなってきます」 こう話すのは東京・巣鴨のベーカリー、アルルオーナーの林春二さんだ。林さんは10年間、洋菓子職人として修業を積んだ後、1967年、東京・北区に洋菓子店をオープンした。 林さんが独立するためにまず行ったことは、50㏄のバイクの購入だった。それに乗って店舗物件を探そうと思ったのだ。1966年、25歳のときだった。「不動産屋さんを当たっては、物件を見に行くという日々が続きました」と林さんは当時を振り返る。 開業資金は当時のお金で170万円。 林さんは、ある信用金庫がやっていた独立を目指す人のための積み立てを行っていた。毎月一定の額を積み立てていって、積み立てたお金の何倍かの金額を融資してくれるというものだった。 当時働いていた店の社長に「自分の店を出したい」と相談したところ、多くの独立開業成功者を輩出していたある菓子店に連れて行ってくれた。林さんは「まだ自分には足りないところがある」と考え、そのときはいったん独立を思いとどまった。 その翌年、開業。それまで世話になった店の社長が保証人になってくれた。共同経営も考えた。しかし「共同経営はうまくいかない。絶対に1人でやった方がいい」とアドバイスされた。 修業するなら小さな個人店がいい 1976年にパンも作り始めた。当初は、冷凍生地を仕入れて焼成していたが、あるときからスクラッチでも作るようになり、徐々にスクラッチにシフトしていった。およそ7年前に、それまで持っていた2店舗を、東京・巣鴨の店舗だけにして、パンの製造販売に特化、現在は、健康志向の個性豊かなベーカリーとして、巣鴨の名物的存在になっている。 林さんは「もし、雇われのパン職人としてずっと働いていくつもりなら、待遇や労働時間などの面からも大きな会社が断然いいと思います。しかし、いつか自分の店を持ちたいのなら、小さくてもキラリと光る個人店の門をたたくに限ります。そのオーナーからすべてを学べますから」。 自分でこつこつと貯めたお金なら、機械ひとつ買うのにも神経を使うはず。 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。