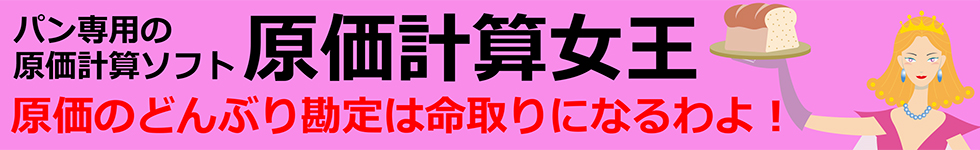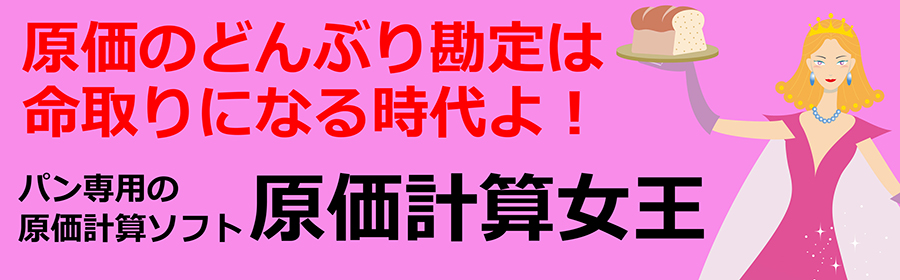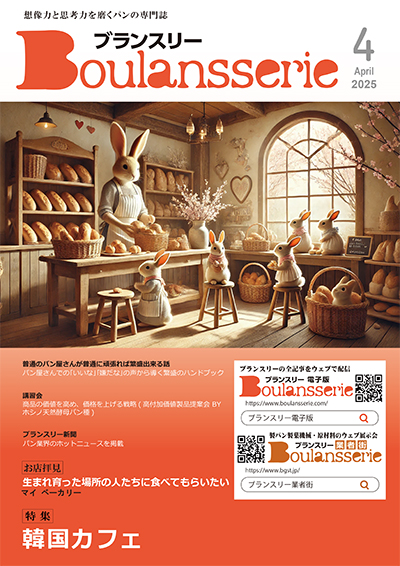記事の閲覧
| <<戻る | 写真をクリックすると拡大写真が見られます。 |
| 食のトレンドを追う/2009年4月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| 値上げもなんのその史上2位の規模に拡大したアイスクリーム市場 | |
|
うだるような暑さの真夏に食べるアイスクリームはたまらないが、冬、暖房の効いた室内で食べるアイスクリームもまた、えもいわれぬ幸せをもたらしてくれる。かつて凋落傾向にあったアイスクリーム市場だったが、2006年度から堅調に規模を拡大。2008年度は、原料価格の高騰による値上げにもかかわらず史上2番目の規模に伸長する見込みだ。市場が回復しつつある背景には、温暖化による猛暑や暖冬の影響もさることながら、メーカー各社の消費者の原点回帰を的確にとらえたマーケティングと販売戦略があるようだ。不遇の時代を乗り越えたアイスクリーム業界がとらえたものとは?
|
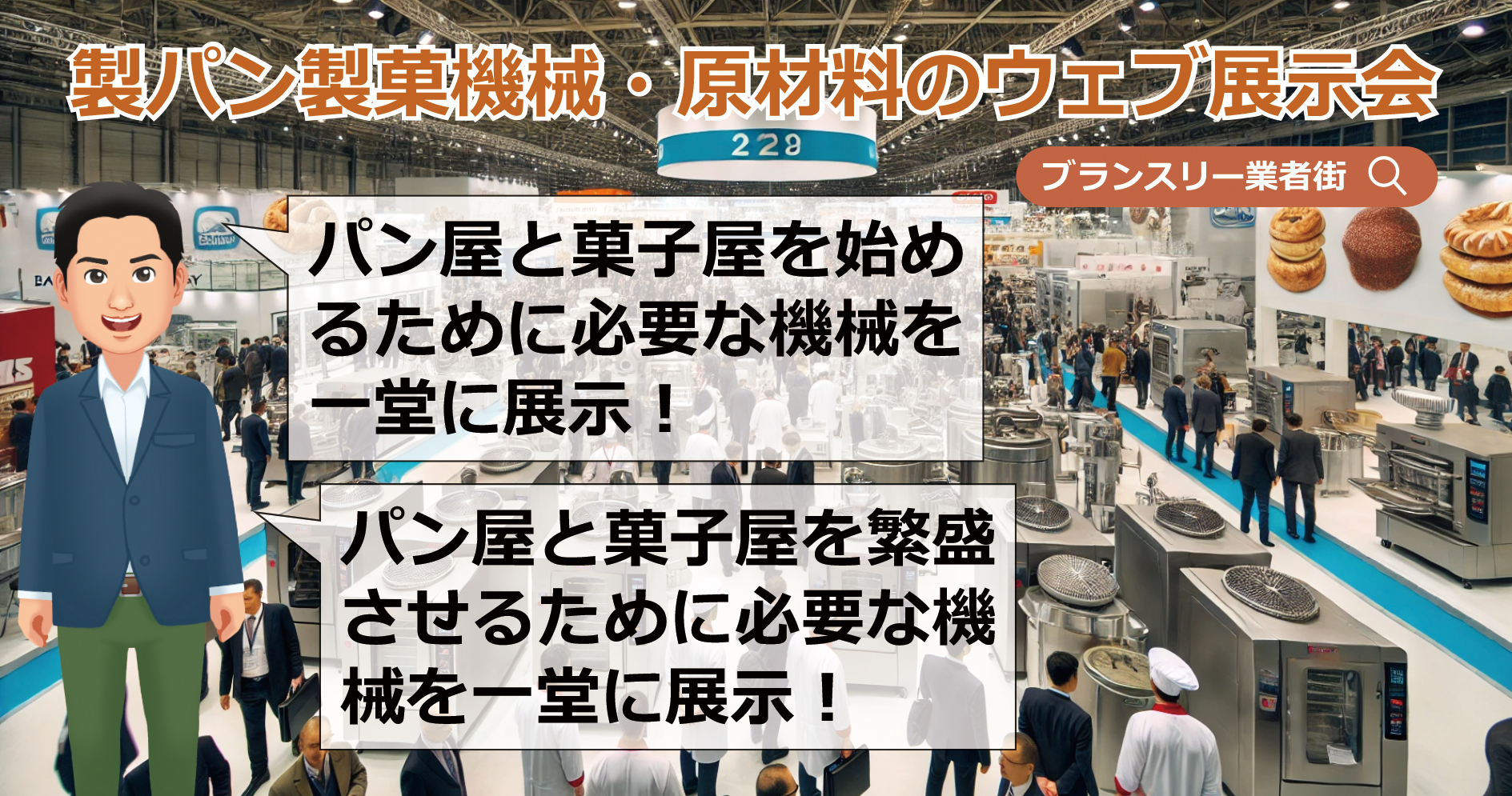
| 9年連続の減少から3年連続伸長へ | |
|
アイスクリーム市場が過去最大の売上を記録したのは、1994年度のこと。日本列島が記録的な猛暑に見舞われたこの年、わずかなお金でひと時の涼が得られるアイスクリームは飛ぶように売れ、およそ4270億円まで市場を拡大した。しかし、この勢いもつかの間。翌年から縮小の一途を辿り、2003年度までじつに9年連続で前年割れとなった。
500ミリリットルのペットボトル飲料の台頭や、次々に開発される新デザートに市場を侵食されたことが低迷の要因といわれている。さらには、携帯電話の普及で消費者の可処分所得が減ったことも一因だという。要するに、人々が携帯にお金をかけるようになり、アイスクリームを買う分の小遣いが減ったというわけだ。 再び猛暑が襲った2004年度は10年ぶりに市場を拡大させたものの、翌2005年度はまたも減少に転じた。このままジリ貧かと思われたが、2006年度、2007年度と伸長を記録。そして2008年度の市場規模も前年比4%超の成長で3800億円程度に着地しそうだと予測されている。これは、1994年度のピークに次ぐ史上2番目の数字である。しかも昨年春には、急激な原材料コスト高騰のあおりで各社とも主力ブランドを100円から120円にするなど値上げに踏み切っている。普通なら消費者離れを生みそうだが、値上げの影響はほとんど見られなかった。 森永乳業の主力商品の1つ、ひとくちタイプのチョコボールアイスとしてお馴染みの「ピノ」も昨年春に20円の値上げを行ったが、数量ベースでも前年を上回っている。さらに同じく主力の「MOW(モウ)」「PARM(パルム)」も堅調だという。 「主力の3商品に加え、ロングセラー商品である『チェリオ』や『クリスピーナ』も好調です。いずれも、お客様から〝この商品なら間違いない〟という信頼をいただいているブランドです。それらのブランドに注力した販売促進や期間限定のフレーバーを発売することで、ロングセラーでありながらブランドの鮮度を保てたのが、好調の要因ではないでしょうか」と語るのは、森永乳業広報IR部の村上友香氏だ。 長年愛されてきた主力商品やロングセラー商品を改めてテレビCMなどでアピールすることで、安全安心志向の高まる消費者の購買意欲を刺激したのだ。ちなみに、板チョコ入りアイスバー「チェリオ」は前年比120%超、コーンアイスの「クリスピーナ」は前年比140%超と大きく伸長している。 |

| マーケティングの見直しで既存ブランドを再強化 | |
|
売上高業界トップを誇るロッテアイスも、主力ブランドが好調で全体の伸びを牽引した。モナカ型アイスの定番「モナ王」は前年比25%増。チョコレートアイスの「ハーシー」も前年比35%増(スーパー向けカップ)を記録している。フルーツアイスの「ドール」、プレミアムアイスの「レディボーデン」なども堅調だ。いずれも、誰でも一度は食べたことがあろうお馴染みの商品。これらの商品が堅調な背景には、「安全安心志向の高まりと景気停滞の影響から、昔から慣れ親しんだ既存ブランド、ロングセラーブランドへの回帰があるのでは」と、ロッテアイス営業統轄部市販用営業部営業企画二課の宮坂隆洋氏は話す。
そうした消費者の回帰傾向を的確にとらえ、ロッテアイスもまた森永乳業同様に主力ブランド、ロングセラーブランドをよりアピールする戦略を展開してきた。たとえば、パーソナル商品を数個箱詰めにしたいわゆるマルチパックの商品をスーパーなどで積極的に販売してもらうことで、商品の集中化・重点化を図っている。値ごろ感のあるマルチパックは、家族で食べるアイスクリームとして主婦層にも人気を得やすい。急激な景気の悪化で消費者の財布の紐が固くなるところを、割安感のあるマルチパックでアピールした点で、巧みな戦術だったといえよう。 ここへきて各社が消費者の安全安心志向をとらえ既存ブランドの再強化に注力しはじめたのは、マーケティングの見直しがあったようだ。 宮坂氏が、自嘲気味に語る。 「9年連続で市場が縮小していたころは、各メーカー間のシェア争いが熾烈であったために、消費者不在のマーケティングに陥っていたと思います。その結果、アイスクリームの商品自体に魅力が乏しかった。ここ3年続けて市場が伸長しているのは、各社が原点に返ってマーケティング施策を対消費者に向けたためだと分析しています」 独自性の高い、従来にはない価値の高い商品開発に取り組む一方で、既存ブランド、ロングセラーブランドのさらなる強化に取り組んだのは、きちんと消費者に目を向けたマーケティングがなされた成果であろう。 前出の森永乳業・村上氏もこう話す。 「ここ数年の好調は、各社のおいしさへの追求、安全、安心への追求努力がお客様の信頼を得られた結果ではないかと考えています。弊社では今後も、お客様の視点というものをさらに強く意識して、消費の変化を迅速にキャッチし、お客様の視点に立った商品開発を強化していきます」 |

| 消費者がアイスに求める精神的価値 | |
|
もともと、アイスクリームは不況に強い商品だともいわれる。
「それは、味覚的満足に加えて、精神的満足を与えることができる数少ない商品だからではないでしょうか。とりわけ、景気の停滞感、社会の閉塞感が蔓延する昨今、精神的満足を求める方が多いのではないかと思います。100円から300円程度と比較的リーズナブルで、かつ日常の『リラックス』『リセット』シーンに活用できるのがアイスクリームという商品の特性ですから」(宮坂氏) アイスクリームの持つ精神的価値については、村上氏も同意見だ。 「お客様は、アイスクリームに物性的価値だけではなく、その商品を買うことによってどんないいことがあるのかという精神的な価値、情緒価値を求めていると思います。食品ですから、『安全であること』『おいしさ』は不可欠ですが、それにとどまらず『幸せな気分になれる』『ホッと癒される』といった情緒的な価値を提供できる商品が支持されていると思います」(村上氏) たしかに、あの独特の冷たさがもたらすのか、アイスクリームには他の食品とは一味も二味も違った幸福感や満足感がある。決して満腹にはならないものの、気分転換や癒しには最適な食品だ。とりわけ既存ブランドやロングセラーブランドは、先行きの見えないこの時代に、〝安心感〟という情緒的な価値で消費者にひとときの癒しを与えている。日常における小さな幸せ。これはすべての食品に求められる命題なのかもしれない。(K) |
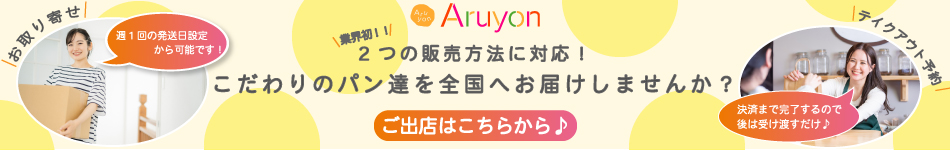
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。