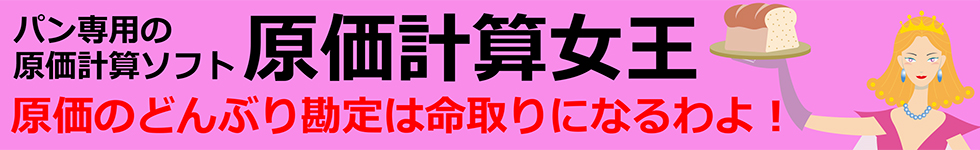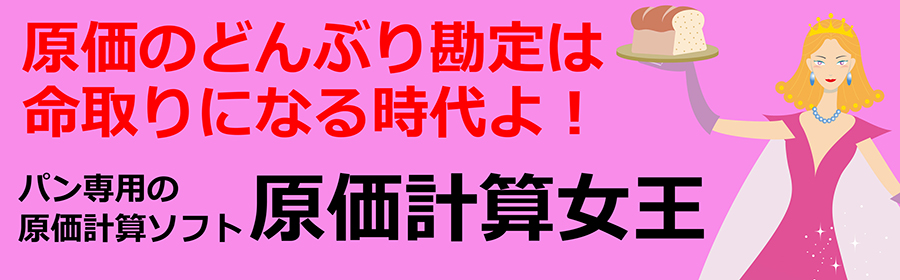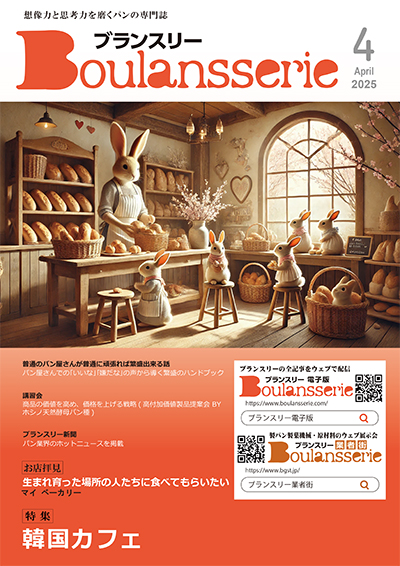記事の閲覧
| <<戻る |
| 特集/2003年11月号 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。
| パンの価格について - ベーカリーのオーナーに聞く
今回は、ベーカリーのオーナーらに、パンの価格について取材してみた。売る側が考える適正価格と、買う側が求める適正価格のギャップを埋めるべく、各ベーカリーとも様々な努力をしている。長引く不況の中で、ベーカリーのオーナーらは、パンの価格をどうとらえているのか・・・
|
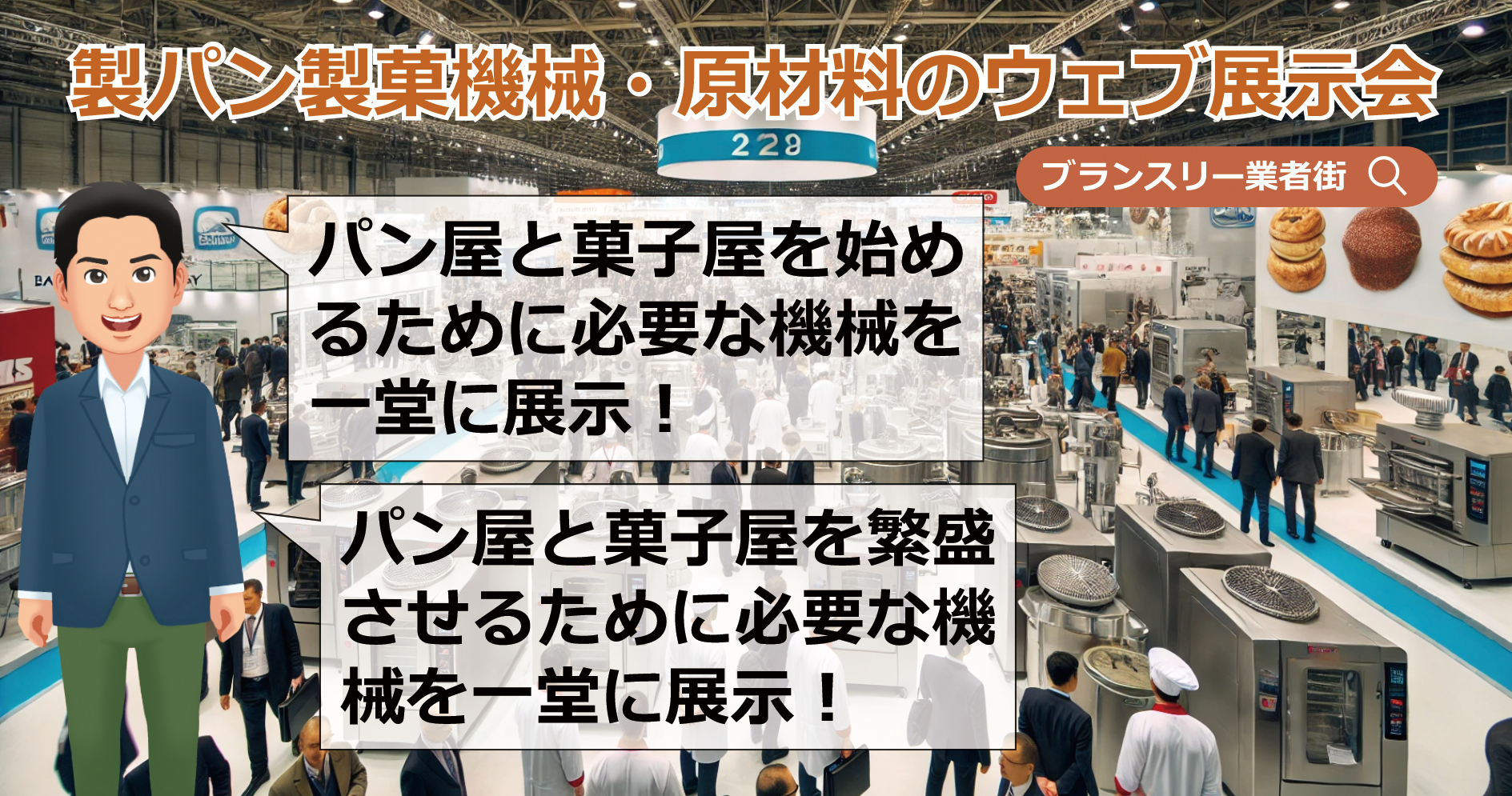
| 食への関心が高い顧客が多く、パンの価値にはかなり厳しい - ラ・フーガス
ラ・フーガスは、小田急線・梅丘駅下車徒歩約3分の場所にある。
有名外食店も多く、住む人、集まる人の食に対する関心度は高い。 ラ・フーガスでは、バゲットとバタール(いずれも生地重量350グラム)が220円、小型のバタール(生地重量180グラム)が130円の価格設定。食パンは、パン・ド・ミ(生地重量440グラム)が220円。角食(生地重量440グラム)が同じく220円。 仁札正男オーナーはこうる・・・ 最終的には経験から決める 私は、原価をはじき出してそれに単純に一定の割合をかけて売価を決めるということはしません。材料の値段は考慮しますが、自分が納得のいかないものは使いません。まずお客様においしいものを提供したいという思いがあります。 新しい商品ができると、スタッフたちに「この商品をいくらだったら買うか」と聞いて参考にします。そして、最終的には自分が判断して決めます。10年間この場所でお客様と関わってきたことから得た感覚で判断します。 材料原価は、毎月、その月に使用した材料費と売り上げとを見て把握します。 包装材とロスの分も原価に入れて、ウチの場合は35%から40%の間です。 このあたりのお客様は、かなりシビアで、いいものはそれなりの値段でも買いますが、値段に見合うだけの価値を認めなければ絶対に買いません。 パン以外の商品も同じで、例えば牛乳やジャムなどで、無農薬であるなど、その商品の価値をはっきりと伝えれば、高くても売れます。 高い場合、強気の価格も 売価を安くしようとして原材料を選ぶことはありません。おいしいものを作ろうとして、結果的に原価が高くなって、それを常識的に言われている原価率に収めようとすると、売価がかなり高くなってしまう場合もあります。 その場合は、原価率がかなり高くなる場合もあるし、強気の値段をつけて、それなりに抑えることもあります。しかし、それなりに抑えたとしても一般的には高いのかなとも思います。 ひとつの例をあげると、以前「バゲットカンパーニュサンド」という商品を出したことがありましたが、かなり品質のいいサラミやマスカルポーネなど使って自分としては自信作でした。 材料費もかなり高かったので、強気の値段をつけました。しかし、あまり売れませんでした。 提案したい場合、原価率高めに 自分が価値があると思っても、お金を出すのはお客様ですから、お客様にその価値をわかってもらうことが必要だと思っています。 逆に「この商品は絶対に自信がある。なんとしても多くの人に食べてほしい」と思った場合に、材料原価に比べて極端に安い値段をつけることもあります。 多くの人は価値を見出せないか、価値があるのかどうかわからないだろうと考えられる場合は、とにかく多くの人に食べてもらうことが先決だからです。普及させたいという思いがあるのです。 この場合難しいのは、地道に提案した結果、価値を理解してくれる人が増えてきたときに、値段を上げられないということです。 正直な話、値段を上げることほど怖いものはありません。こうした場合は、同じ材料を使って、違う形の商品にして出します。 |

| 顧客に価値を理解してもらう、同じ材料で違う商品を作る - パン焼き人 パン焼き人は、東急東横線・都立大学駅から徒歩約10分の目黒通り沿いにある。ベーカリーとレストランがあって、ベーカリーは厨房が約6坪、売り場が約4坪。レストランは約10坪。
人気商品には、「クスクス」というセモリナ粉を原料にした極少パスタを配合して作る無発酵のパンや、ニンニクとコーンミールを練り込んだパンなどユニークなパンが多い。 イギリス食パン(生地重量400グラム)が270円。内麦粉で作る「昔の食パン」(生地重量400グラム)が300円。バゲット(生地重量350グラム)が260円。 安井定義オーナーはこう語る・・・ 作り手と買い手のギャップを埋める 使う材料の仕入れ値と、売価の相場との関係で、例えばフランスパンなどは、原価率が低く、菓子パンなどは原価率が高くなる傾向があります。私の場合は、まず、全商品の原価率を25%にするようにしています。 商品を新しく作るときは、一番グレードの高い材料を集めて、材料に妥協することなく、試作します。そして原価から考えて妥当と思われる値段をはじき出します。それが、私が妥当と考える価格です。 しかし、作り手は「これだけの材料を使って、これだけの技術と手間をかけて作ったのだから、このくらいが適正価格」と考えても、買い手としたら「できるだけいいものをできるだけ安く」と考えるわけで、どうしてもそこにギャップが生じます。私は、スタッフや家内に製品を見て味わってもらい、意見を聞くことにしています。たとえば私としたら500円で売りたい商品があったとして、スタッフや家内の意見が450円だった場合、ひとつの方法として中間をとって470円にしたりします。これは原材料をより安いものに代えたら、商品が意図したものではなくなるという場合です。 材料を代えて、価値が高まることも これとは違って、材料を最初に考えたものより安いものに置きかえて、まったく問題がないか、逆にもっと面白いものができる場合もあります。 例えば、「マロンクロワッサン」という商品があるのですが、これは最初ミルフィーユをパン生地で包んだ商品をと考えていたのですが、パイ生地が高かったので、発想を変えてジェワーズを、クロワッサン生地で包んだ商品にしました。マロンペーストの代わりにマロンクリームを使ったり、洋栗ではなくて、和栗を使ったりしました。いずれにしても、材料を代えたことによって、品質が落ちることがあっては絶対になりません。代えたことによって違う面白さが出てこなくてはなりません。 出店当初は、原価率高かった ウチの場合は、珍しいパンが多いので、お客様としたら最初はなかなか手が出しづらいということはあると思います。店を出した当初は、そうした事情から今より平均売価は安かったと思いますね。材料費が安かったということではなく、原価率が高かったということです。35%ぐらいはあったと思います。ウチの商品が叙徐々にお客様に馴染んできて、充分に価値がわかっていただけるようになってきて、現在の25%ぐらいになってきました。原価率がそれなりで、材料もそれなりにいいものを使っているので、多分売価は世間の平均より高いのではないかと思います。 出店当初と比べたら売価が少し上がっているわけですが、同じ商品を上げるわけにはいきません。同じ材料を使って目先を変えた商品を作るのです。そういうことを繰り返しているうちに、商品の入れ替わりが進み、今の状態になりました。 しかし、バゲットとか、シンプルな食パンなど、どうやっても変えられないものもあります。そういう商品は昔のままの値段です。 それと、材料屋さんに掛け合って、仕入れ値を下げてもらう努力もしています。「ウチはこの材料を年間でこれだけ使うのだから」といって掛け合います。 10代の顧客開拓も考えたい ウチは、気に入ったものだったら、それなりの値段でも買っていただけるお客様が多く、そうしたお客様だけで充分やっていける状態です。そういう意味では恵まれているのだと思います。ただ、新たな顧客開拓ということを考えると、今のままではいけないと思うこともあります。例えば10代の人たちなどです。ウチのお客様にはほとんどいないのですが、10年後、20年後のことを考えると、そうした人たちが無理なく買えるような価格設定も考えていかなければならないと思っています。 |

| 全体の材料原価は、35%。立地的に値頃感が必要 - ベルドール ベルドールは、大阪府富田林市のベーカリーだ。街道沿いのスーパーの近くの立地で、リーズナブルな価格設定を打ち出している。あんぱん(生地重量40グラム、あん50グラム)が、100円。角食が生地重量440グラムで180円。
奥光義オーナーはこう語る・・・ 付近のパンの価格を調査して決める 天然酵母のパンで、生地に何も入っていない場合は生地の重量で1グラム0・5円を基準にし、レーズンやナッツ類などが入っている場合は1グラム1円を基準にします。それ以外は、原価との兼ね合いで決めています。 周りのパンの値段の相場を調査して参考にします。 全体の材料原価は、ロスの分も入れて35%程度です。立地的に、高い価格は設定できません。 多くの場合、これぐらいで売りたいという値段があって、それをもとに材料を選定していきます。 例えば、ウチで最もよく売れている食パンは1斤180円ですが、原価率は高めです。 かといって粉にしてもほかの材料にしてもグレードを落とすわけにはいきません。 サイズの問題で悩むことが多い 多くの場合、新商品を考えるときは、例えば、「デニッシュでもう一品ほしい」とか、「菓子パンを強化したい」などと考えることから始まります。よくほかのベーカリーに見に行ったりするのですが、デニッシュを強化しようと思っているときは、デニッシュばかり見ています。本をみたりもして、いろいろなところからアイデアをもらって、それを自分流にアレンジします。例えば「この菓子パンの形はデニッシュに使ったら面白い」などといった具合です。 商品の具体像がかたまり、材料が決まったら、値段を決めるわけですが、高い価格設定はできませんので、次に問題になるのが、サイズです。これぐらい大きい方がおいしいと思ったり、小さくして値頃感を出した方がいいと考えたり、いろいろと悩みます。 親しみある材料が好ましい これまでの経験からいうと、お客様にとって親しみ深い材料でないと、いくら自分がおいしいと思っても、なかなかわかってもらえないようです。ピーカンナッツを使ったときも、あまり売れませんでした。お客様が食べたことがあって、味を知っているもの、少なくても見たり聞いたりしたことがあるものでないとなかなか難しいように思います。 こだわった材料を使うときは「果たしてこの価値をわかってもらえるだろうか」という不安があります。例えばアーモンドクリームでも「アーモンドプードルをたくさん使っておいしく仕上げてあるということが、果たしてわかってもらえるか」などと気をもんだりします。 |

| 価格は、材料原価から一律にはじき出す - アルル アルルは、東京・巣鴨のベーカリー。
マスコミにもたびたび登場する人気店。ホームページにも力を入れていて、新規顧客開拓に一役買っている。 小麦粉と塩と水だけで作る「古代パン」やキャロブ粉をトッピングした「キャロブ、オマメパン」など個性豊かな商品が多く、巣鴨の名物的存在になっている。 食パンで最もよく売れる「天然酵母パン」は生地重量400グラムで250円。 林春二オーナーはこう語る・・・ 地元客と遠方からの客の違い パンの価格は、材料費を正確にはじき出して、それが一定の原価率になるように決めています。パソコンを活用してほぼすべての商品について同様に決めます。 また、作る手間の度合いも考慮します。手間がかかるものについては、その分多少売価を高くします。 この場所で長い間商売をしてきて思うのは、地元のお客様と遠方から来るお客様との傾向の違いです。 まず、地元のお客様は、菓子パン系、遠方からのお客様は、食事パン系という違いがあります。 さらに、客単価の違いがあります。地元のお客様は低く、遠方からのお客様は高くなります。 |
| 以前と比べたら、やはり高いものは売れなくなった。 - ベルアルプ ベルアルプは、東京・巣鴨の地蔵通り商店街にある。黒五や発芽玄米など様々な材料を使ったパンの開発に積極的で、熱心なファンも多い。
食パンは、最もよく売れるものが1斤180円。内麦を使った1斤250円の食パンも以前は売れ行きがよかったが、最近は180円のものにシフトしてきているという。 地引弘道オーナーはこう語る・・・ 売りたい値段と買いたい値段 ウチの場合は、包装材、ロスも含めて原価率は32%ぐらいです。個々の商品の原価率については、使う材料と価格の相場との関係でもともと高いものと安いものがあります。フランスパンなどは安いし、調理パン関係は高くなりますね。 値決めのノーマルな方法は、原価率が一定の割合になるように設定することだと思いますが、見た目(大きさやフィリング、トッピングなどの感じ)に対して、お買い得感をつけたいという思いは常に持っています。 「原価から計算した価格では、見た目の印象からして、かなり高く感じるが、自分としてはどうしても売りたい」というときは原価率が高くなっても、ぎりぎりのところまで値段を低くします。 例えば、最近出した「ライ麦のくるみパン」という商品があります。くるみが30%入っていて、生地重量150グラムのナマコ型のパンですが、私としては200円はほしいと思いました。しかし、スタッフらに聞いたりした結果、200円では高いということになり、170円で売っています。私としたらかなり安くしたつもりだったのですが、お客様の立場からしたら、「それでも高いかな」という感じでした。実際に販売してみると、それなりに売れています。 製造日限定で、1回に10個程度の製造量ですが、売れ残ることはほとんどありません。ライ麦パンなのでボリュームもあまり出なくて、見た目は確かに割高な感じがしますが、トングで持ったときに大きさの割にずしっと重いことと、ライ麦自体が注目されていることなどが、よかったのだと思います。原価率は約35%と高めですが、コンビニやスーパーなどに対して専門性をアピールするという意味でも、よかったと思っています。 強気の値段の時は試食を提供する 逆に、かなり強気の値段をつけることもあります。あるとき、発芽玄米を使ったパンを出したのですが、発芽玄米がかなり高くて、480グラムの生地重量で420円に設定しました。自分としたらかなり強気な値段でしたが、想像以上によく売れています。 ただ、全体的な傾向としては、価格が高いものは売れなくなってきています。1斤180円の食パンと1斤250円の食パンがあるのですが、3年前と比べると、250円の方は販売数がかなり減っています。180円の方に流れてきていますね。 自分なりに自信があって強気の値段をつけた場合は、試食を積極的に提供します。 試食といえば、最近はカットして商品の前に置いておくのではなく、「この商品は試食ができます」と書いた試食カードを置くようにしています。お客様の方から「試食したい」といってきたら、お客様の前でカットして、提供するのです。こうすることで、「つまみ食い」がなくなり、本当に試食したいお客様だけに絞り込めるようになりました。 |
| しっかりとした基準が必要。高原価率商品はロスを避ける - ベーカリーコンサルタント、橋本泰之氏の話
新商品が完成して、原価をはじき出し、売価が120円になったとします。パートの女性スタッフに聞くなど、買う側の立場になって検討してみて、「120円では高い。100円が妥当だ」という結論になったらば、同じ原価で売価だけを下げるのではなく、材料を再検討するなどして、原価率を同じに保って同じ商品を作るにはどうしたらいいかを考えます。
いきあたりばったりで考えてもだめで、やはりしっかりとした基準を持つことが大切だと思います。基本的には、オーナーが理想とする原価率は保つべきだと思います。私の場合は、さまざまな条件はあると思いますが、包材も入れて30%が上限だと考えています。 売れている分野の商品にさらに力を入れるべきです。どんなパンが売れるかは、売り上げをチェックすればすぐにわかるので、その分野の品揃えをさらに強化すべきです。売れるものをさらに売ることが商売の基本です。その際に、その分野、例えば菓子パンだったら、菓子パンのなかで、どの価格帯の商品が少ないかをチェックして、その価格帯の商品を作るようにすべきだと思います。一方で、「売れる数量は少ないが、必要な商品」も地道に作っていくようにします。いずれの場合も理想とする原価率は極力保つように心がけるべきです。 こうしたことを続けていくうちに、店の個性が鮮明になってきます。 ただ、原価率が例外的に高いものがあってはいけないとはいっていません。戦略的にそうする場合もあると思います。しかし、そうした場合は、例えば時間限定で販売するなどして、ロスを出さないように工夫すべきです。 いずれにしても、商品開発や価格設定は、しっかりとした基準を持って、行わなくてはなりません。 |
2023年11月18日から、発行から1年を経過した記事は、会員の方以外にも全文が公開される仕様になりました。